
STORYストーリー
「八百屋兼レストラン」という新しいスタイルでオーガニックな日本の農家を応援し、野菜で感動を提供したい。
- 槇村野菜笑店
- 槇村賢哉
- (まきむらかつや)
槇村野菜笑店は、農家から直接取り寄せた野菜を販売する八百屋兼レストランだ。モノトーンの落ち着いた店内。黒い壁面には赤、緑、黄色といった色とりどりの野菜が、まるで絵画のように美しく陳列されている。「ショーケースに並ぶ野菜を見ながら食事できるレストランがコンセプトです」と語るのは、オーナーシェフの槇村賢哉さん。ホテルマンを経て29歳でオーガニックの八百屋を独立開業。志半ばで一度廃業するが、飲食店の統括マネジャーやレストランの予約システムに関わる仕事を経て、ふたたび八百屋を開くことになった。以前との違いは野菜を食べるレストランを併設したこと。「最終的にやりたいのは八百屋です。日本の農家を応援したい。だからこそこの業態を選びました」。槇村さんのレストラン経営には、その背景に “野菜を廃棄したくない”という想いがある。野菜を売るだけでなく、保存方法やソース作りなど、技術を磨いて料理として提供することで、野菜を無駄なく使えるようにする。実際、仕入れた野菜をほとんど使い切ることができているそうだ。“八百屋になりたい若い人をもっと増やしたい”という槇村さんに “未来の八百屋のカタチ”について話を聞いた。
キャリアのスタートはホテルマン
私は小さな頃から今も変わらず、人を喜ばせたり、人を笑わせることが好きです。子どもの頃の得意科目は美術と体育。とはいえ美術大学や体育大学への進学は難しいと感じていたところ、父親から「人を喜ばせることが好きなら接客業だ。その頂点はホテルだろう」と、ホテル専門学校のパンフレットを手渡されました。ちょうどバーテンダーが主役の映画が流行っていた頃で、「こんなバーテンダーになりたい!」と憧れて、ホテル専門学校に通うことを決めました。入学後、校長先生に「いいホテルで研修したいです!」と直訴して、紹介されたヒルトン東京(現ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ)で研修を受けることになりました。
配属されたのは憧れていたバーテンダーではなく、ベルマンの仕事でしたが、多様なお客様と接するホテルの仕事は楽しく、卒業後はそのままヒルトン東京に就職しました。その後、沖縄のリゾートホテルや、グランドハイアット福岡でのコンシェルジュを経験してきました。ホテルの仕事は楽しいし、人と接することで磨かれる部分も多い。でも次第に、独立して自分の事業をやりたい思いが芽生えていきました。自分のやりたいことを自分の責任でやりたい。30歳までに独立することを目標に、行動をはじめました。

「エコ」の考え方に共感し有機野菜の八百屋を開業
世紀末となる1999年は、なんとなく未来への不安がある時代でした。僕自身も人口拡大・環境破壊への危機感を感じていました。「これから地球はどうなっていくのだろう?」と考えていたとき、ふとエコが今後のキーワードになるのではと思いました。当時ネットでエコを検索してもほんの数件がヒットするぐらい。その1つが長野県にあるエコロジーショップでした。「エコって何だろう?」が知りたくて、直接現地を訪ねるとそこには八百屋がありました。
店主に話を聞くと「政治家でもない私たちが世の中にできることは限られる。だから小さなことから行動を変える。農薬を使わない農家を応援することもエコにつながるんだ」と教えられました。農業を起点に地球全体の土や水の循環を考え、環境を守っていく考え方が「かっこいい!」と思い、東京の福生市で有機野菜を扱う八百屋を開業しました。

再起をかけてさまざまな経験を積む
でも、時代が早すぎました。エコは今でこそ当たり前の言葉ですが、世の中には浸透していませんでした。商売を軌道に乗せることは難しく、奮闘しましたが3年で廃業することになりました。そこで当面は野菜に関わりながら、さまざまな経験を積んでいこうと、オーガニック野菜を販売していた表参道のショップに転職をしました。仕入れの知識を活かして野菜のバイヤーになるつもりで入社したら、ホテルでのサービス経験があるならとレストラン部門に配属されました。
そこで初めて料理に興味を持つようになりました。お客様に説明をするためにシェフに教わったり、個人的にもちょこちょこ料理をするようになりました。その後、飲食店を複数経営していたオーナーに誘われ、統括マネジャ−として顧客管理や予約システムの導入に携わりました。その仕事がきっかけとなり、予約システム会社を経営している知人から声をかけられ、事業拡大に自分の経歴が活かせると思ったこと、また野菜をWebサイトで販売する新規プロジェクトが立ち上がることにも興味を持って転職を決めました。
野菜は楽しい。もう一度八百屋がやりたい
野菜を商品として扱えることになり、高級レストランには、美味しい野菜を扱うバイヤーとして、営業をしました。シェフと料理についての会話をしながら、求められる野菜を仕入れたり、こちらからの提案をきっかけに、信頼を得て予約システムの導入を次々と決めていきました。シェフからは新しい農園を教えてもらうことも多く、「野菜はやっぱり楽しいな!」と、自分が本当にやりたかったことを再認識しました。
2014年、八百屋を再開することに決め、レストランへの卸から事業をはじめました。あるとき料理教室の経営をはじめた方から、手伝って欲しいと声をかけられました。ソムリエのワイン講座をするけど料理がないと。「それなら私が作りましょうか」と、野菜をフル活用した料理を提供したところ、みんなが「美味しい!」と喜んでくれました。それがすごく嬉しかった。ワインの会は評判となり、予約枠が埋まるようになりました。人を喜ばせることはやっぱり楽しいし、それが自分にとって一番のやりがいになると気がつきました。「料理もやればいいじゃん!」とみんなが言ってくれたことにも背中を押され、現在の八百屋兼レストランの営業スタイルをはじめることにしました。

“八百屋目線”の美味しい野菜料理

槇村野菜笑店という店名には「野菜で笑顔に!」という想いを込めました。席数が限られているので、現在は完全予約制でランチ6品、ディナー10品のコース料理を提供しています。コンセプトは、八百屋の目線で、野菜の味・香り・食感を最大限に活かした料理を提供すること。味付けは素材を活かしてなるべくシンプルに。魚やお肉、果物も使った意外な食材の組み合わせや、美しい野菜の色合いを、目で見ても楽しめるような料理に仕上げています。
扱っている野菜はすべて私が八百屋としておつきあいしてきた農園のもの。生産者の顔もわかるし、農園のストーリーも語ることができます。昔と違ってエコが浸透し、有機野菜を扱う商店やスーパーも増えましたが、ここ槇村野菜笑店でしか買えない農園の野菜や果物があり、それがお店の大きな特色となっています。旬の時期にしか食べられない珍しい野菜等、季節やそのときどきの品揃えでメニューが変わり、何度もリピートしてくれる常連のお客様が増えてきました。

「Air ビジネスツールズ」は経営パートナー
「この野菜をどう料理したら喜んでもらえるだろう?」と考えてばかりいるので、事務作業にかかる負荷をなるべく減らしたかった。そんな私の大きな助けとなっているのが「Air ビジネスツールズ」です。最初は『Airレジ』『Airペイ』から使い始めて、予約管理システムの『レストランボード』、シフト管理サービスの『Airシフト』、経営サポートサービスの『Airメイト』と、次々導入をしていきました。最近使い始めて本当に便利だなと感じているのは『Airカード』です。
必要経費はすべてカードで支払っているので、『Airメイト』と連携してお金の動きがすべて管理できるようになったことが便利だし、それだけでなく1.5%のポイントがつくのが最高ですよね。経費は毎月それなりの金額が発生するので、どんどんポイントが貯まり、必要な物を買うことができています。お店を経営している人には絶対おすすめ。私にとっては手放すことのできない経営パートナーのような存在です。

どうすれば野菜で感動を提供できるか

小さな店舗ですし、コロナ禍では本当に大変な思いをしました。でも続けることもやめることも、どちらも地獄なら続けることを選ぼうと決め、お弁当やケータリング、宅配等、できることに懸命に取り組んできました。危機を何とか乗り越え、今ようやく商売が軌道に乗ってきたところです。29歳で有機野菜の八百屋を開業し、一度挫折をしてからかれこれ20年以上。農園とのつきあい、野菜の知識も増え、料理や保存・加工の技術を磨き、課題であった野菜の廃棄もほぼしなくて済むようになりました。廃棄を無くすことはエコの基本でもあるし、持続可能なお店になるために大事なことだと思っています。
振り返るといろいろな仕事をしてきましたが、最終的に自分がやりたいのは八百屋です。経営を続けていくにはどんなスタイルのお店にするかも大事だし、扱う野菜や農園について、しっかり語れることも大事だと、経験を通して学びました。時代の変化に合わせてやり方も変わっていくと思うけれど、「日本の農家を応援する」という軸はぶらさずに、若い人たちが憧れて、自分もやってみたいと思うような八百屋になっていきたい。ただ野菜を売るだけではなく「野菜って美味しい。感動する。だから買いたい!」を提供する八百屋になれたら、かっこいいですよね。それが今後も八百屋が生き残っていくスタイルになるんじゃないかと思っています。

- 槇村野菜笑店
- 東京都港区南青山2-20-1
- 03-5772-2111
この記事を書いた人
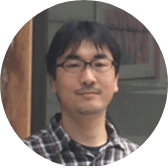
羽生 貴志(はにゅう たかし) | ライター
ライター。株式会社コトノバ代表。「コトのバを言葉にする」をコンセプトに掲げ、いま現場で起きていることを、見て、感じることを大切に、インタビュー記事や理念の言語化など、言葉を紡ぐことを仕事にしています。
https://www.kotonoba.co.jp
前康輔(まえ こうすけ) | 写真家
写真家。高校時代から写真を撮り始め、主に雑誌、広告でポートレイトや旅の撮影などを手がける。 2021年には写真集「New過去」を発表。
前康輔 公式 HP http://kosukemae.net/
