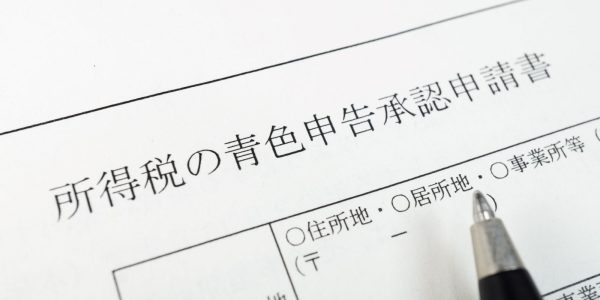合同会社(LLC)とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説
穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士

会社の設立をする際、注目を集めているのが「合同会社(LLC)」という会社形態です。株式会社に比べ、株主総会や決算公告といった手間が省けるため設立費用や運営コストが抑えられ、意思決定のスピードも速いのが大きな魅力です。実際、アップルやグーグルなど世界規模の企業の日本法人でも合同会社という形態を採用しているほか、年々設立数も増加しています。
本記事では、合同会社の基本から、メリット・デメリット、具体的な設立ステップなどをわかりやすく解説します。自分の事業プランに合った選択をするためのヒントにぜひ役立ててください。
この記事の目次
「合同会社」とはどんな会社?
まずは合同会社の基本を解説します。株式会社や合資会社など、ほかの法人形態との違いを整理しましょう。
合同会社(LLC)とは?
合同会社(ごうどうがいしゃ)は、株式会社や合名会社、合資会社と並ぶ会社形態の1つです。英語ではLLC(Limited Liability Company)と言います。
2006年施行の会社法改正で導入された比較的新しい形態ですが、合同会社の設立件数は年々増加し、現在は株式会社に次いで多く、新設法人の約3割にも及んでいます。
合同会社では、お金を出した人(出資者)がそのまま経営者(社員)になり、全員がほぼ対等な立場で会社の方針を決められます。さらに、万が一会社が倒産しても各人が失うのは出資したお金の範囲内だけで済む「有限責任」のため、個人の生活まで大きく巻き込まれにくい仕組みになっています。
合同会社の社員が出資者・経営者
株式会社では株主と経営陣が分離しているのが一般的ですが、前述のとおり合同会社では出資者=経営者です。このため経営方針を決める際のフローがシンプルで、スタートアップのようにスピードが求められる場面で威力を発揮します。
合同会社のフラットな意思決定体制を活かせば、例えば日々の売れ行きを見ながらメニュー価格を微調整したり、即日でキャンペーン内容を変更してSNSに反映したりと、現場で得たデータをそのまま経営判断に結び付けることができます。
加えて、広告の出稿先や予算配分をリアルタイムで最適化したり、配達エリアを急きょ拡大・縮小して需要の高い地域へリソースを集中させたりといった対応も可能です。このように、マーケットの動きに合わせた細かなチューニングを短いサイクルで回せる点が特徴と言えるでしょう。
合同会社の役職
法務局へ登記できる役職は下記3つです。
| 役職 | おもな役割 |
|---|---|
| 代表社員 | 会社を外部に代表し契約行為を行う |
| 業務執行社員 | 日常業務と経営を直接執行(代表社員を兼務可) |
| 社員 | 出資者として経営判断に参加(出資比率は自由) |
「社長」や「CEO」は登記上の肩書ではありませんが、商号や名刺、ウェブサイトで自由に名乗ることは可能です。例えば「代表社員+名前」で表記すれば、法的要件(代表社員の記載)とビジネス慣習上のわかりやすさ(CEOや社長の肩書)を両立できます。
合同会社には形式的な「取締役会」は存在しませんが、代表権を持つ人物=代表社員が実務上のトップとして機能しつつ、必要に応じて「社長」「CEO」「COO」といった職務呼称を併用できる柔軟な仕組みになっています。
合同会社の設立費用
設立方法によっても費用は変わりますが、合同会社を設立するために最低限必要な費用は、6万円程度です。株式会社と比較して、非常に安く設立できるのが合同会社の大きな特徴の一つです。下記の法定費用のほかには会社の実印作成に数千円~、証明書発行に数百円程度かかります。
| 項目 | 紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 6万円~ | 6万円~ | 法務局での登記費用(資本金の0.7%または6万円のどちらか高い方。100円未満の端数があるときは端数金額は切り捨て) |
| 定款の収入印紙代 | 4万円 | 0円 | 電子データ(PDF等)で定款を作ると、印紙代がかからない |
大手企業でも合同会社形態がある
合同会社は小規模事業者向けというイメージを持つ人もいますが、実際にはアップルジャパン合同会社やアマゾンジャパン合同会社のように、世界的企業が合同会社で設立しているケースがあります。理由は、日米でLLC概念が共通し管理コストを削減できるからです。この実績が「合同会社=信用が低い」という従来の印象を大きく変えています。
合同会社と株式会社の違い
次に、合同会社と株式会社の特徴(設立費用や資金調達など)を比較してみましょう。
| 比較項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 設立費用 | 定款認証不要(作成は必要)/登録免許税6万円〜 | 定款認証約5万円+登録免許税15万円〜 |
| 会社の所有者 | 各社員 | 株主 |
| 会社の代表者名称 | 代表社員 | 代表取締役 |
| 意思決定 | 社員の同意 | 株主総会・取締役会で承認 |
| 経営の自由度 | 高い | 低い |
| 役員任期 | 任期なし | 最長10年 |
| 信用度 | 徐々に改善もまだ劣る | 国内で最も一般的で高評価 |
| 決算公告 | 義務なし | 官報・Webで公告必須 |
| 資金調達方法 | 限定的 | 幅広い |
| 株式市場への上場 | できない | できる |
| 利益配分 | 自由 | 出資比率による |
| 社会的信用 | 株式会社よりは低い | 高い |
このように比較してみると、会社が倒産した場合などの責任が有限責任である点は共通しているものの、違う点も複数あります。例えば、設立費用。コストを抑えて素早く意思決定できる環境を重視する場合は、合同会社が有利であることが分かります。
一方、上場や大規模な資金調達を視野に入れており、取引先や金融機関からの社会的信用を第一に考えるのであれば、依然として株式会社のほうが有利でしょう。つまり、スタートアップ段階で「身軽さ」を優先したいなら合同会社、事業規模の拡大を前提に「資金と信用」を確保したいなら株式会社というように、自社の成長戦略に合わせて選択肢を切り分けるのが賢明と言えるでしょう。
合同会社と株式会社の略称
株式会社であれば略称は、「(株)」ですが、合同会社の略称は「(同)」です。金融機関での振込みでは、「(ド)」と表記されるのが一般的です。
合名会社・合資会社との違い
合同会社と似た名称である合資会社、合名会社とも比較してみましょう。いずれも「持分会社」に分類されますが、無限責任社員の有無が大きな違いです。
| 比較項目 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 |
|---|---|---|---|
| 社員の責任 | 全員有限責任(負債は出資額まで) | 全員無限責任(個人資産でも返済) | 無限責任社員+有限責任社員の混在 |
| 設立コスト | 公証役場認証不要/登録免許税6万円〜 | 合同会社とほぼ同額 | 合同会社とほぼ同額 |
| 意思決定 | 全社員で合意→即決 | 無限責任社員が主導 | 無限責任社員が主導 |
| 決算公告義務 | なし | なし | なし |
| 資金調達 | 株式発行不可/信用度は中程度 | 株式発行不可/信用度低 | 株式発行不可/信用度低 |
| 採用例 | 新設件数が増えている | 家族経営などごく少数 | ほとんどない |
無限責任を負う合名・合資会社は、創業者がすべてのリスクを背負う覚悟が必要になるため、近年ではほとんど選ばれなくなりました。
その点、合同会社は出資額を超えて個人資産を差し出すリスクがないうえに、設立コスト・運営コストも低いといったメリットが揃っています。こうした「有限責任+低コスト」という組み合わせが、現代のスタートアップや小規模ビジネスにとって最適解となりつつあり、持分会社の中で圧倒的に支持されている理由です。
個人事業主との違い
個人事業主とも比較してみましょう。合同会社は法人の一形態であり、個人事業主とは大きく異なる存在です。
例えば、資金調達の手段に違いがあります。個人事業主は、他人から出資という形ではお金を調達することができません(借入れでの資金調達は可能)。一方、合同会社は法人なので、第三者から出資を受けることができます。出資を受ける必要性がある場合は、合同会社を含め法人という形態で事業を始めるのが有効です。
さらに大きな違いとして、責任の範囲もあります。個人事業主は「無限責任」のため、事業で負債が生じた場合は自身の個人資産を使ってでも返済しなければなりません。一方、合同会社の社員(出資者)は「有限責任」であり、仮に会社が倒産しても、自らが出資した金額の範囲内でしか責任を負いません。つまり、個人の生活資金や不動産などが差し押さえられるリスクは原則としてありません。こういった点からも、事業の成長性やリスク管理を見据えるなら、法人化、とくに合同会社の設立は現実的な選択肢となるでしょう。
会社形態別の設立数
会社形態別の設立数は、2023年の政府統計によると株式会社が約71%、合同会社が約29%となっています。合同会社は、株式会社に次いでメジャーな形態といえるでしょう。
| 会社種類 | 設立数 | 設立割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 100,669件 | 71.17% |
| 合同会社 | 40,751件 | 28.81% |
| 合資会社 | 17件 | 0.01% |
| 合名会社 | 15件 | 0.01% |
合同会社のメリット・デメリット
この章では合同会社の利点と注意点をご紹介します。双方を照らし合わせながら、ご自身の事業計画に本当にフィットするか検討してみてください。
合同会社のメリット
まずは合同会社のメリットについて確認しましょう。
設立コストが低く、維持費も抑えられる
まず、会社の設立費用が株式会社よりも低くなります。株式会社であれば約20万円~かかりますが、合同会社であれば6~10万円程度で設立可能です。コストに加え、定款認証というプロセスが不要なため、設立にかかる時間も短くなります。また、決算公告義務もないため、株式会社より安く運営できます。
経営の自由度が高く、意思決定が速い
株主総会や取締役会を開く必要がなく、チャットや少人数会議で決議して実行が可能です。ITスタートアップや飲食業など、市場変化が激しい業種に向いています。
利益配分を自由に決められる
合同会社では配当のルールを定款で自由に設計できるため、「出資額は少なくても営業実績が突出したメンバーには利益を厚く分配する」といった成果連動型の仕組みを持たせることが可能です。出資比率だけでは測れない日々の貢献度を報酬に反映しやすい点は、社員のモチベーション維持にもつながるでしょう。
役員任期の制限がなく手続きがラク
合同会社には株式会社のような取締役任期(最長10年)がなく、任期満了ごとの変更登記も不要です。そのため、更新のたびに発生する司法書士への依頼料や印紙代がかからず、コストと事務負担を抑えられます。
決算公告の義務がない
合同会社は法律上、決算内容を官報やウェブサイトで公開する義務がありません。広告費用を気にせずに済むうえ、競合他社に売上や利益水準を知られにくいので、コスト削減と情報秘匿の両面でメリットがあります。
有限責任なので個人リスクが抑えられる
社員は出資額の範囲でしか責任を負わないため、万が一会社が負債を抱えて倒産しても、個人の財産まで差し押さえられる心配がありません。個人事業主の「無限責任」と比べると、リスクを限定したうえで事業に挑戦できる仕組みです。
株式会社への移行が比較的容易
事業が成長し、株式発行や上場を視野に入れた段階で、合同会社から株式会社へ「組織変更」を行うことができます。新たに会社を作り直すより手続きがシンプルで、法人の歴史や契約関係をそのまま引き継げる点が大きな利点です。
合同会社のデメリット
次に合同会社のデメリットについて確認しましょう。
信用度や認知度が株式会社に比べて低い
合同会社は2006年の会社法施行で作られた新たな法人形態で、認知度は株式会社より低く、国内の商慣習では長年使われてきた株式会社のほうが安心感を与えるのが実情です。
大規模な資金調達が難しい
合同会社は株式を発行できないため、大規模な資金調達ができません。数億円単位の投資を目指すビジネスモデルの場合は、早い段階で株式会社へ移行する準備が必要です。
出資者同士が対立すると経営に影響
全員が経営に携わるフラットな構造は魅力ですが、意見が真っ向から食い違ったときに調停役がいないと意思決定が止まる恐れがあります。定款に議決ルールや最終決裁者を明記し、対立時の手順をあらかじめ決めておくことが不可欠です。
上場できないため成長戦略に制限がある
合同会社は法律上、株式上場(IPO)が認められていません。将来的に株式市場を通じて資金調達や企業価値の向上を図りたい場合は、組織変更を前提にしたロードマップを描く必要があります。
承継・権利譲渡がやや複雑
社員の持分を第三者に譲渡する際、原則として他の社員全員の同意が必要です。株式ほど流動性が高くないため、経営者交代や事業承継をスムーズに行いたい場合は、譲渡手続きを簡略化できる条項を定款に盛り込んでおくと安心です。
合同会社が向いているケースとは?
ここでは、合同会社がフィットしやすい代表的な4つのケースを紹介します。
小規模なスタートアップや家族経営で始めたい人
「設立コストを極力抑えつつ、とにかく早くサービスをローンチしたい」。そんなスタートアップに合同会社は最適です。例えば開発チーム3人でSaaS事業を立ち上げる場合、登録免許税6万円だけで法人化でき、株主総会も取締役会も不要です。アイデア出しから実装・リリースまでのサイクルを途切れさせずに回せるため、プロダクトの改善速度そのものが競争力になります。家族経営でも同じメリットがあり、役員任期の更新登記が不要なため、法務コストとバックオフィス負担を最小限に抑えたまま長く事業を続けられます。
個人事業主から法人化を検討している人
フリーランスや個人事業主として売上が伸び、所得税率が高くなってきたら法人化による節税が現実的な選択肢になります。合同会社であれば、設立費用が低いだけでなく、利益の取り分も柔軟に決められるため「事業主報酬をいくらに設定し、どこまで法人に利益を残すか」という最適解を見つけやすいのが強みです。
BtoCの商売でスピード感を重視したい人
ECサイト、D2Cブランド、飲食デリバリーなど、消費者ニーズが日々変わるビジネスでは、意思決定スピードが売上に直結すると言っても過言ではありません。合同会社なら、キャンペーン内容の変更や広告費シフトなどを、その日のデータを見ながら即断即実行する体制を構築できます。社内で「代表社員+業務執行社員」の合意さえ取れれば書面決議だけで完結するため、タイムロスなく施策を試行–検証–改善のPDCAに乗せられます。
上場する予定がないが、法人化で信頼を得たい人
地方でリフォーム業を営む、あるいは小規模ながら長期的に安定収益を見込むサービス業など、上場や大規模資金調達をそもそも計画していないケースも少なくありません。こうした事業では、合同会社で法人格を取得するだけでも金融機関や取引先からの信頼度が個人事業主より向上します。決算公告義務がないため財務情報を開示せずに済み、同時にランニングコストも抑えられるので、「信用力アップ」と「経費節減」をバランス良く両立できます。
合同会社設立の流れ
株式会社とは手続きが異なる点も多いため、「合同会社をどうやって作るのか」を6つのステップに整理しました。順番どおりに進めれば、最短2週間程度で設立できます。
STEP1.事前準備
STEP2.会社の基本情報を決める
STEP3.会社用の印鑑を作成
STEP4.定款を作成(公証役場の認証は不要)
STEP5.出資金(資本金)の払い込み
STEP6.設立登記の申請
STEP1.事前準備
最初にビジネスモデルと数字の骨格を固めます。提供する商品・サービスの内容、対象顧客、想定単価を洗い出したうえで、月次の売上と固定費(人件費・家賃・広告費など)を試算しましょう。その結果から「必要資本金はいくらか」「自己資金で足りない分をどう調達するか」が見えてきます。ビジネスモデルが具体的であるほど、後工程の定款作成や出資比率の決定がスムーズです。
STEP2.会社の基本情報を決める
商号(会社名)・本店所在地・事業目的・資本金・社員(出資者)構成を確定します。商号には必ず「合同会社」を含める必要がありますが、同一同業でも登記は可能です。ただしウェブ検索で競合に埋もれない独自性が望ましいでしょう。本店所在地を自宅にする場合、賃貸契約で「法人登記可」かどうかを必ず確認してください。事業目的は将来の業種拡大を想定し、やや広めに書くのが鉄則です。
STEP3.会社用の印鑑を作成
登記に使用する法人実印をはじめ、銀行取引用の銀行印、日常書類用の角印を準備します。実印は法務局へ届け出るため、長期的に摩耗しにくい黒水牛やチタン素材が安心です。実印と銀行印を分けておくと盗難・紛失リスクを下げられます。
STEP4.定款を作成(公証役場の認証は不要)
合同会社の定款には、目的・商号・本店所在地・社員の氏名・出資額などの絶対的記載事項に加え、利益配分や議決方法などを自由に盛り込めます。株式会社と違い公証人の認証が要らず、電子定款を選べば印紙代4万円もかかりません(紙の定款の場合は必要)。ただし定款は会社の基本ルールになるため、利益配分ルールや社員の退社手続きなどを曖昧にせず、専門家のチェックを受けておくと安心です。
STEP5.出資金(資本金)の払い込み
定款が完成したら、各社員が自分名義の銀行口座に資本金を振り込みます。振込明細や通帳コピーは払込証明書として登記書類に添付するので、大切に保管しましょう。なお合同会社は1円からでも設立できますが、取引先や金融機関の印象を考慮し、将来の運転資金も踏まえて適切な金額を設定することが重要です。
STEP6.設立登記の申請
最後に、設立登記申請書・定款・払込証明書・代表社員の就任承諾書など一式をまとめて法務局へ提出します。登録免許税は最低6万円で、窓口・郵送・オンラインのいずれでも申請可能です。書類に不備がなければ受理から1〜2週間で登記が完了し、会社の登記事項証明書と印鑑証明書が取得できるようになります。ここまで終われば、税務署への届出や法人口座開設、社会保険手続きへ進む段取りです。
合同会社設立で失敗しないためのチェックポイント
設立コストと機動力で大きな魅力を持つ合同会社ですが、「設立しやすい=必ず成功する」わけではありません。
実務の現場では、出資者どうしの行き違いや定款の不備が原因でトラブルに発展するケースも少なくありません。ここでは、創業初期に押さえておくべき4つのポイントを解説します。
出資者どうしで役割分担と決裁ルールを明確にする
合同会社は全員が経営者としてフラットに意思決定できる反面、最終責任者があいまいだと合意形成が滞る恐れがあります。定款や別紙協定書で「業務執行権限」や「最終決裁者」を文書化し、誰が何を担当し、どの範囲で決裁できるのかを明確にしておきましょう。
定款へのルール明記を怠らない
利益配分、持分譲渡、社員の退社手続きなどは、曖昧にすると必ず火種になります。ネットのひな型をコピーするだけでなく、司法書士や弁護士に目を通してもらい、自社の事情に合った条項へブラッシュアップしましょう。後から変更登記を繰り返すより、最初に手間をかけるほうが結果的に安上がりになるケースがほとんどです。 また、IPOを視野に入れるなら、設立時点で株式移行の条件(取得条項付持分など)を定款に盛り込むと、後の組織変更がスムーズです。
専門家や支援サービスを活用してスムーズに
会社設立、開業準備は時間と予算がかかるものです。特に初めての場合、準備に不安を抱えている人は多いでしょう。最近は開業を支援するサービスが増えています。税理士などの専門家相談サービスをはじめ、店舗開業に必要な会計、決済、経営支援ツールをまとめて相談できるAir ビジネスツールズの「開業支援セット」など、さまざまな支援がありますので、積極的に活用しましょう。
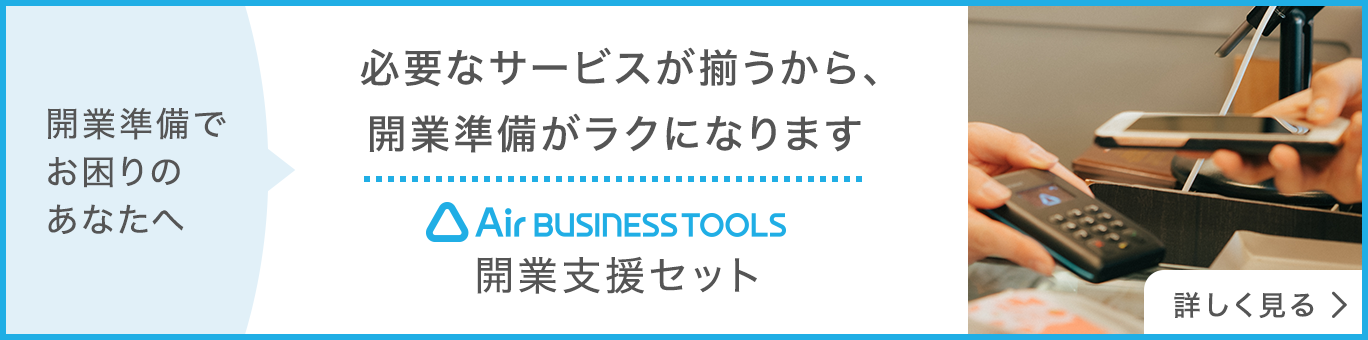
合同会社に関してよくある質問(FAQ)
Q.合同会社にするメリットは何ですか?
A.低コスト・意思決定の速さ・利益配分の自由度・役員任期更新不要がおもなメリットです。
Q.信用度が不安です。株式会社のほうがいいですか?
A.大口融資や大企業との取引が前提なら株式会社が有利ですが、契約実績や売上次第で信用差は縮まります。アップルやグーグルも合同会社を採用している点は大きな後押しとなります。
Q.個人事業主からの法人化はいつがベスト?
A.売上が増え所得税の最高税率が近づいたら検討しましょう。社会保険料負担とのバランスを見極めるため、税理士にシミュレーションしてもらうのが確実です。
まとめ
- 合同会社とは株式会社よりも設立しやすく柔軟性が高い会社形態
- 合同会社はベンチャーや初期投資が少ない会社におすすめ
- 資金調達・信用度を優先するなら株式会社も視野に入れる
- 設立時は専門家&開業支援を活用しスムーズに進めるのが◎
合同会社は株式会社よりもコストが低く設立でき柔軟性に富む一方、資金調達や信用力で制約を受ける場面もあります。自社の事業フェーズと成長プランを踏まえ、必要に応じて株式会社への組織変更も視野に入れた戦略を描けば、リスクを抑えつつ最大限の成長を目指せるでしょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?
- 現金払いだけでいいのか不安…
- カード使える?と聞かれる…
導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。
 ※画像はイメージです
※画像はイメージです
下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。
この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。
-160x160.jpg)
穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士
税理士法人 エンパワージャパン 代表税理士 1981年生まれ 横浜市在住
中小企業こそ日本を支える礎であるという理念から、持続可能な社会・持続可能な企業を創るための「中小企業のための財務支援プログラム」を実施することで強固な財務力を持つ優良企業に導く、中小企業の財務支援に専門特化した税理士事務所を運営するとともに、児童養護施設の児童から地域を支援する税理士へと導く「大空への翼プロジェクト」を行っている。共著「七人のサムライ」や執筆など多数。