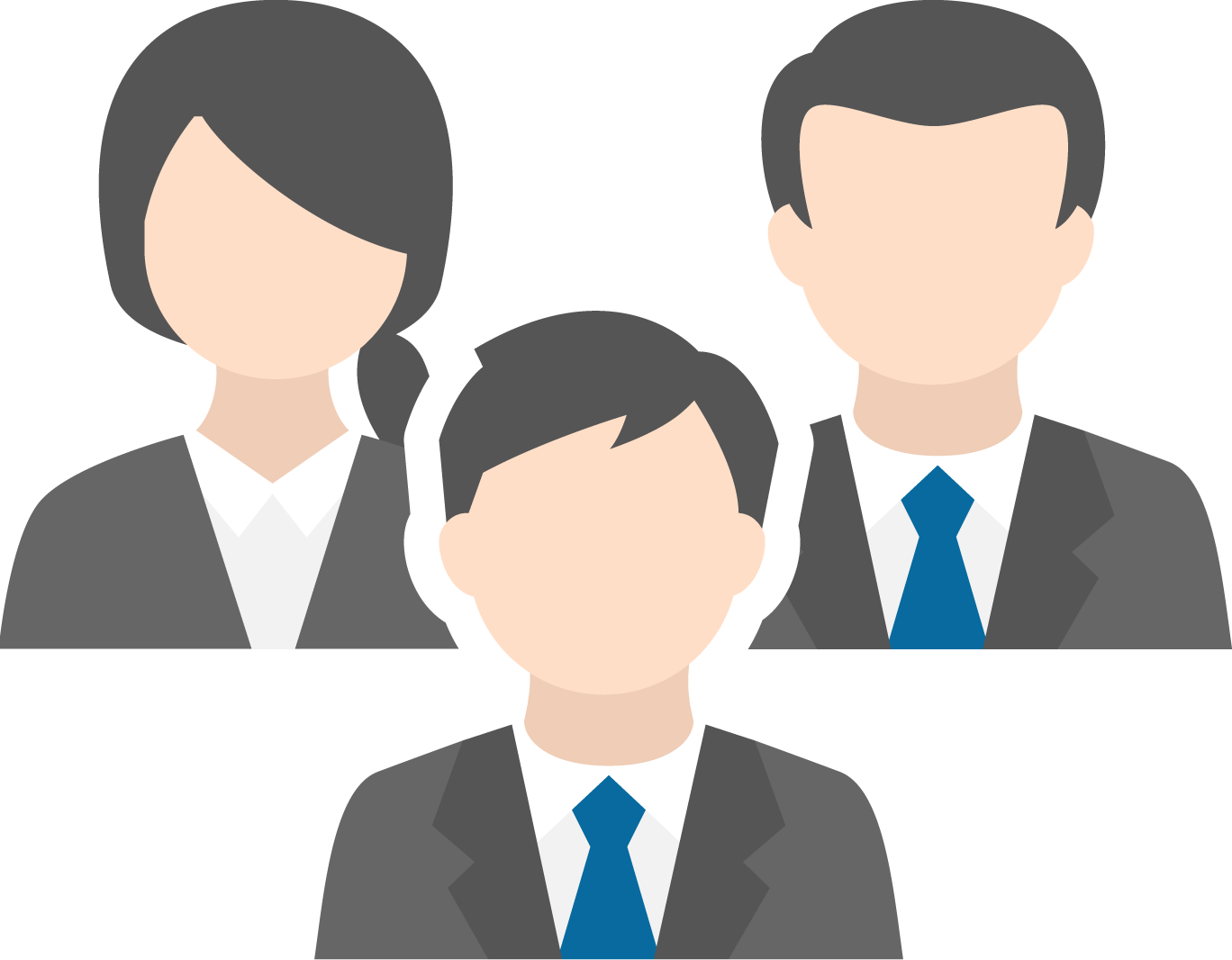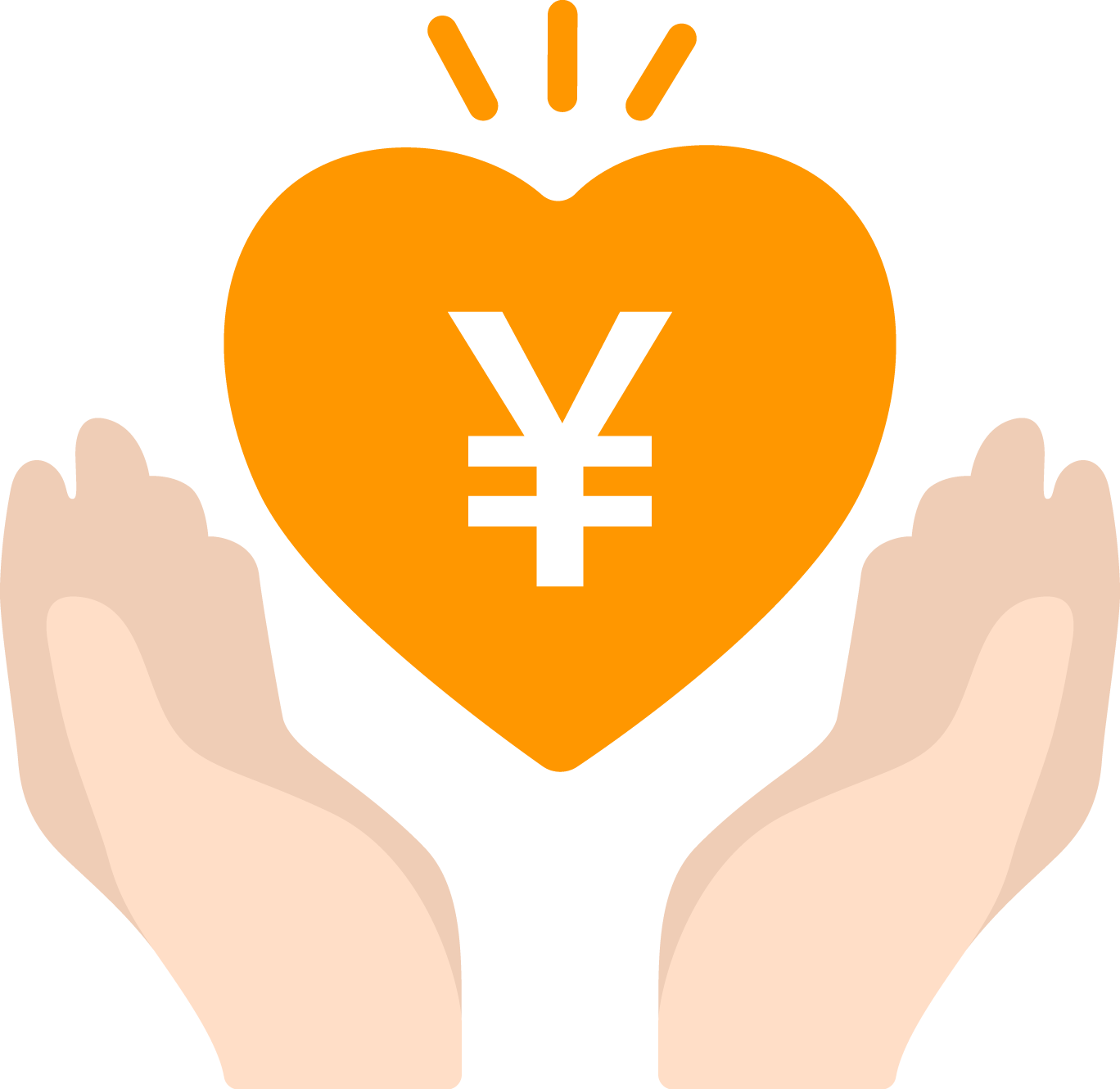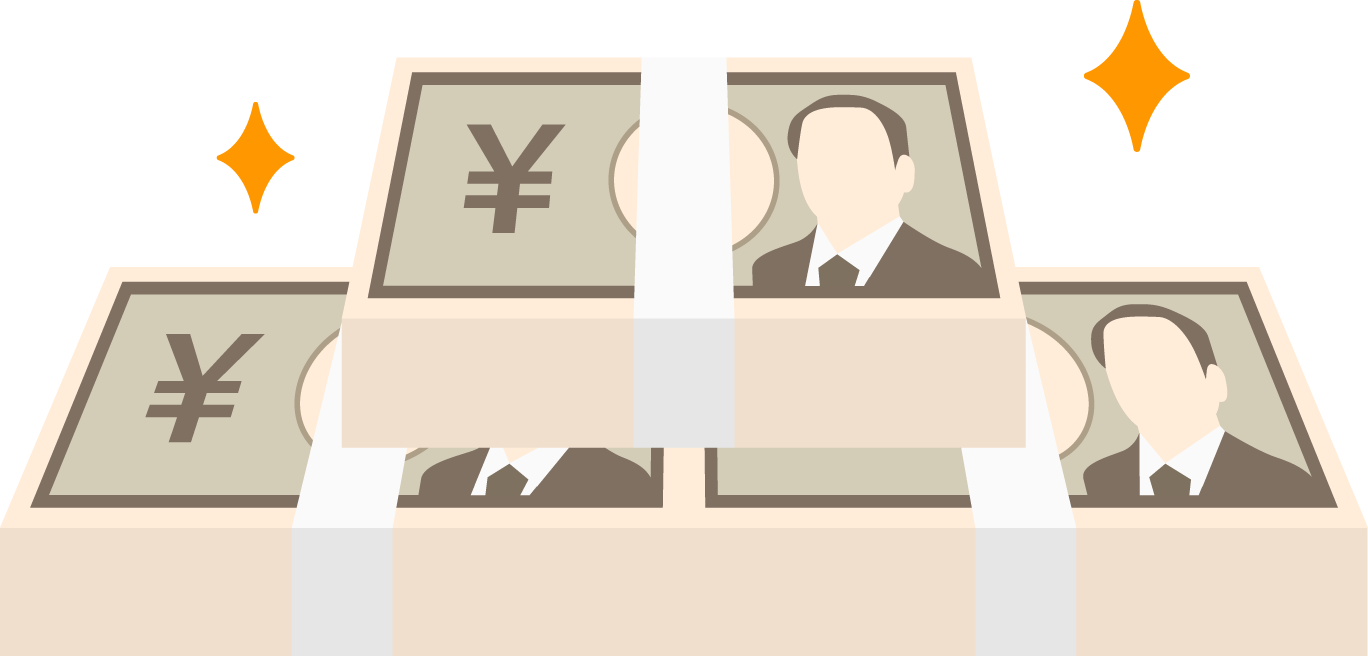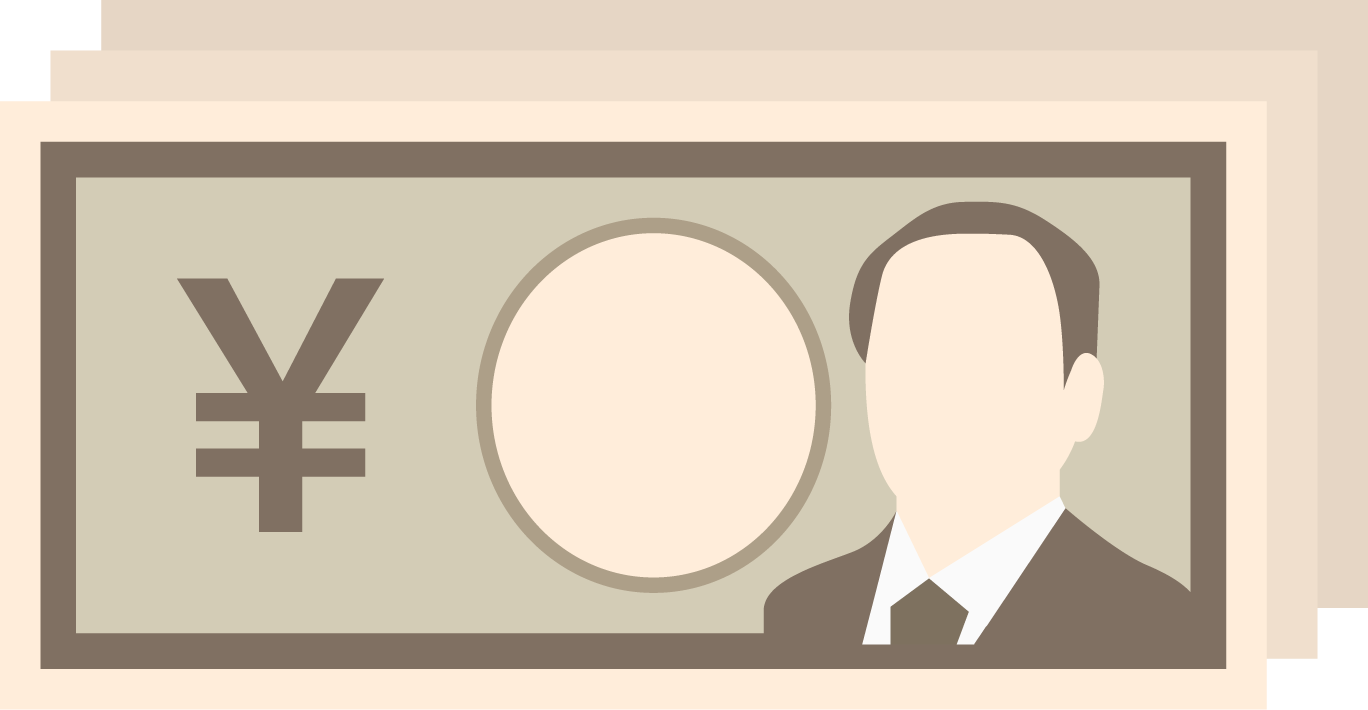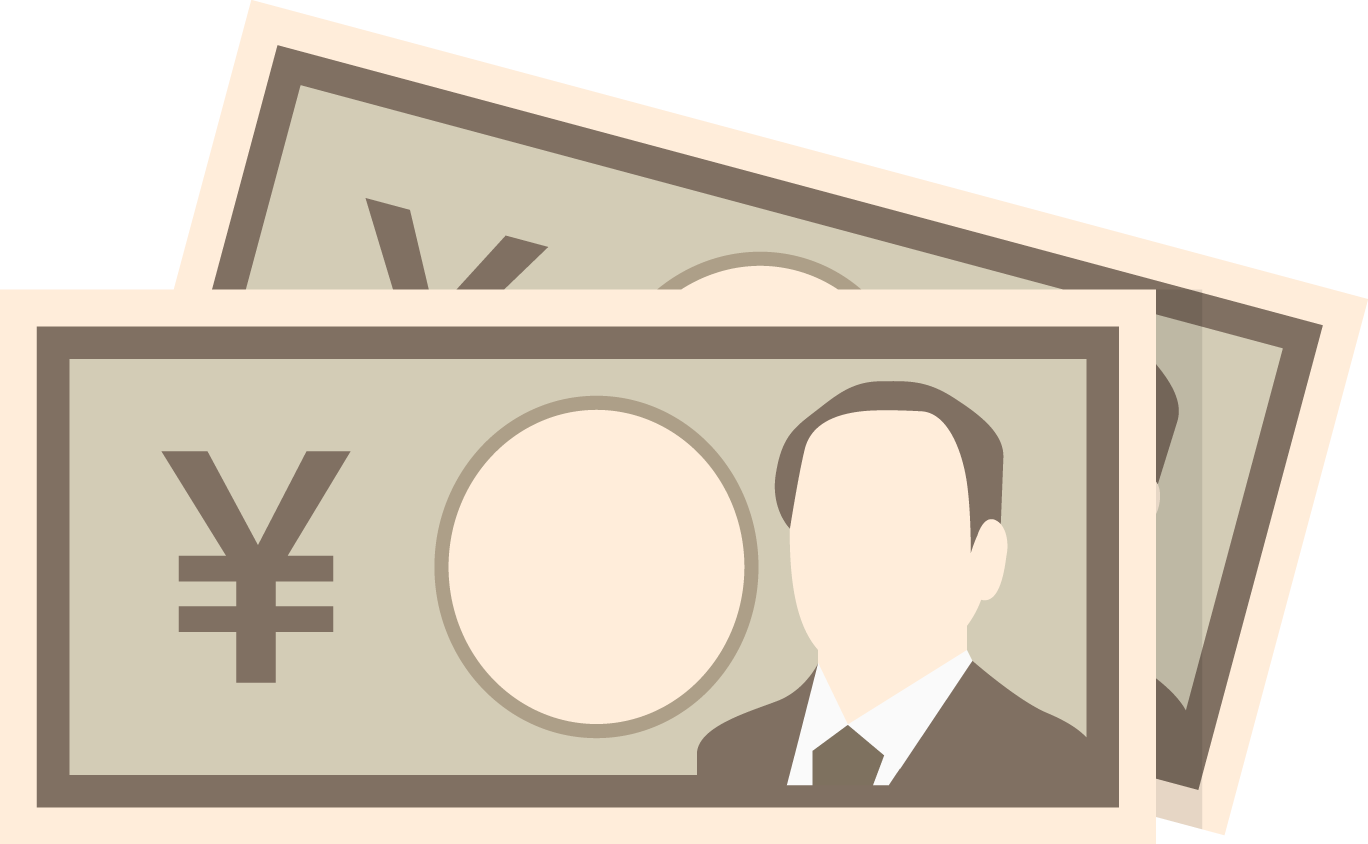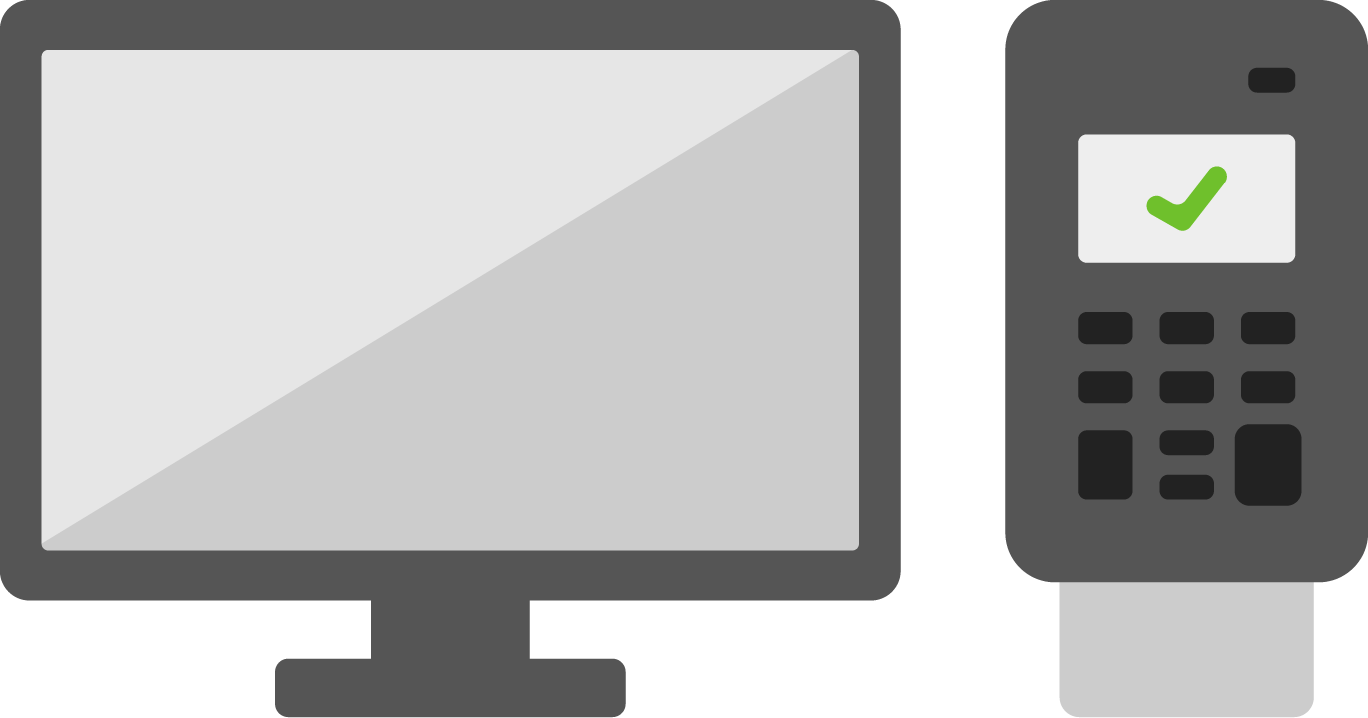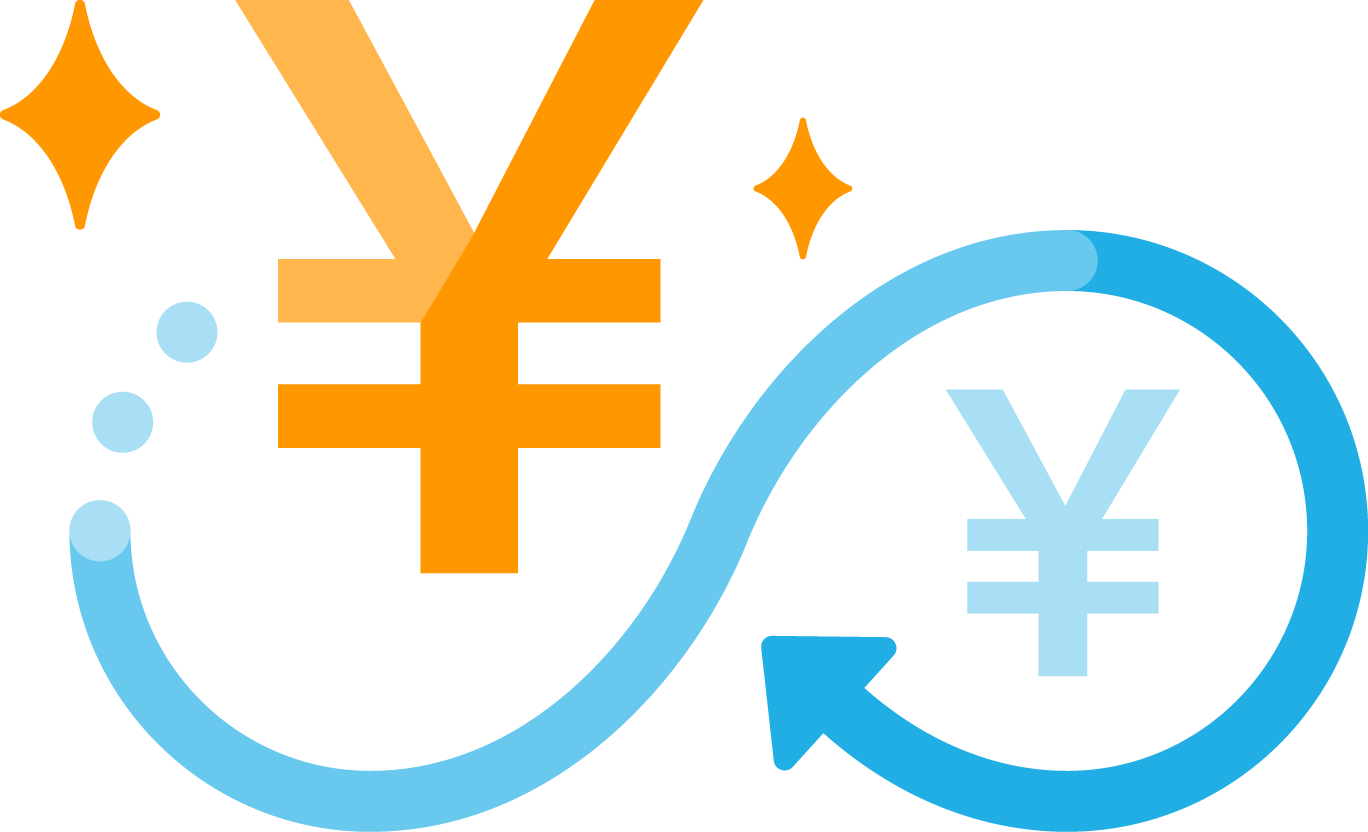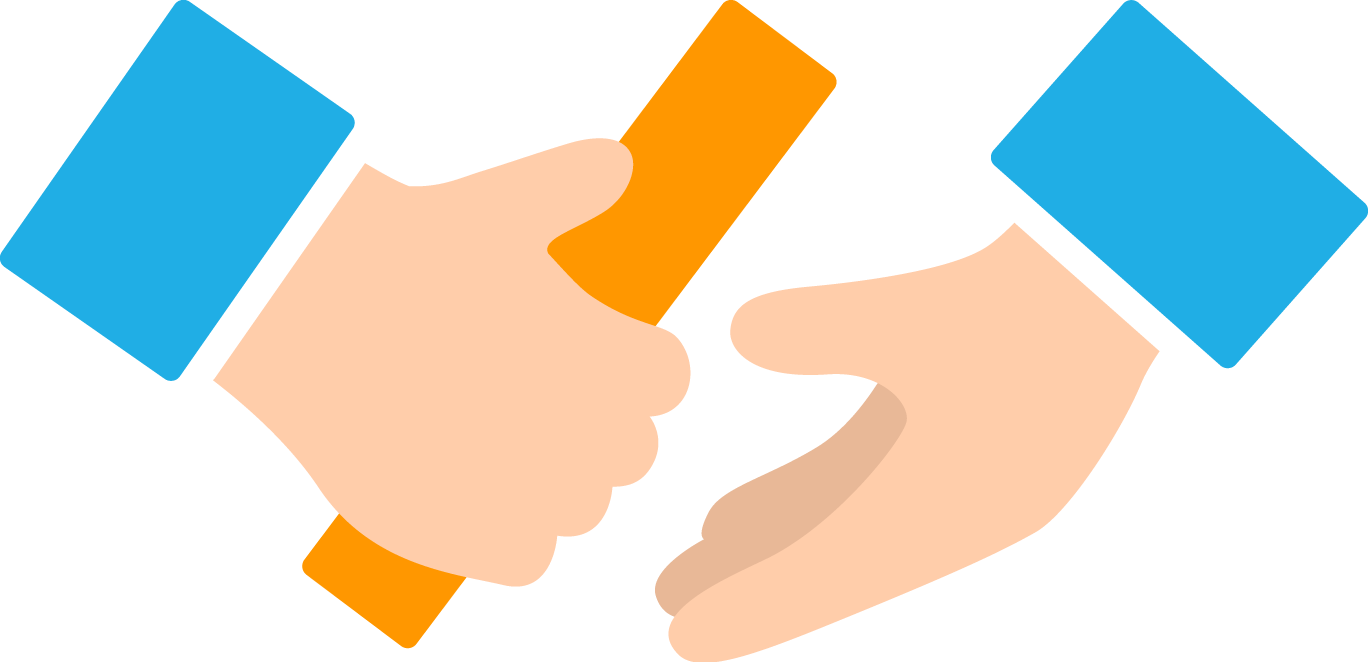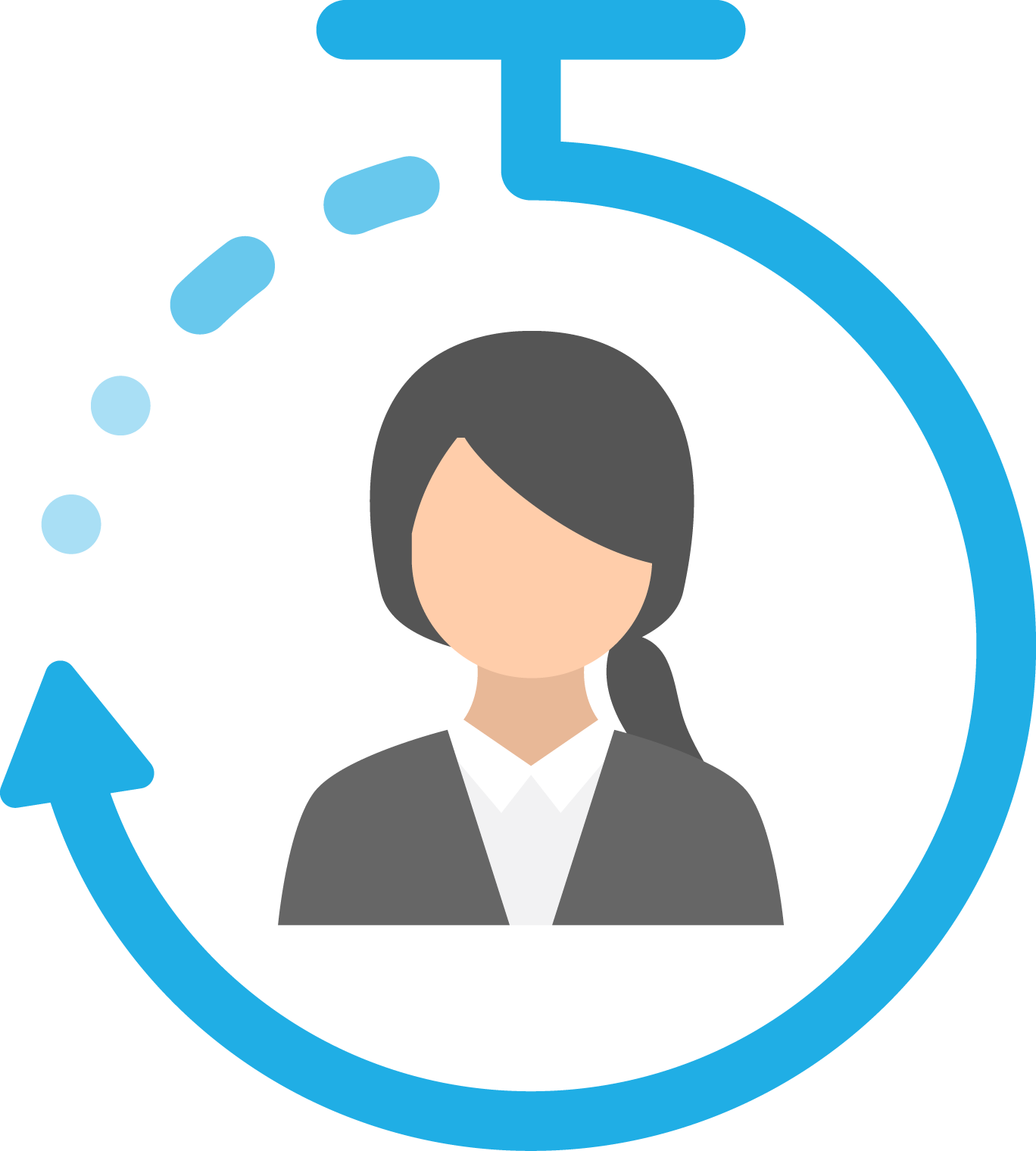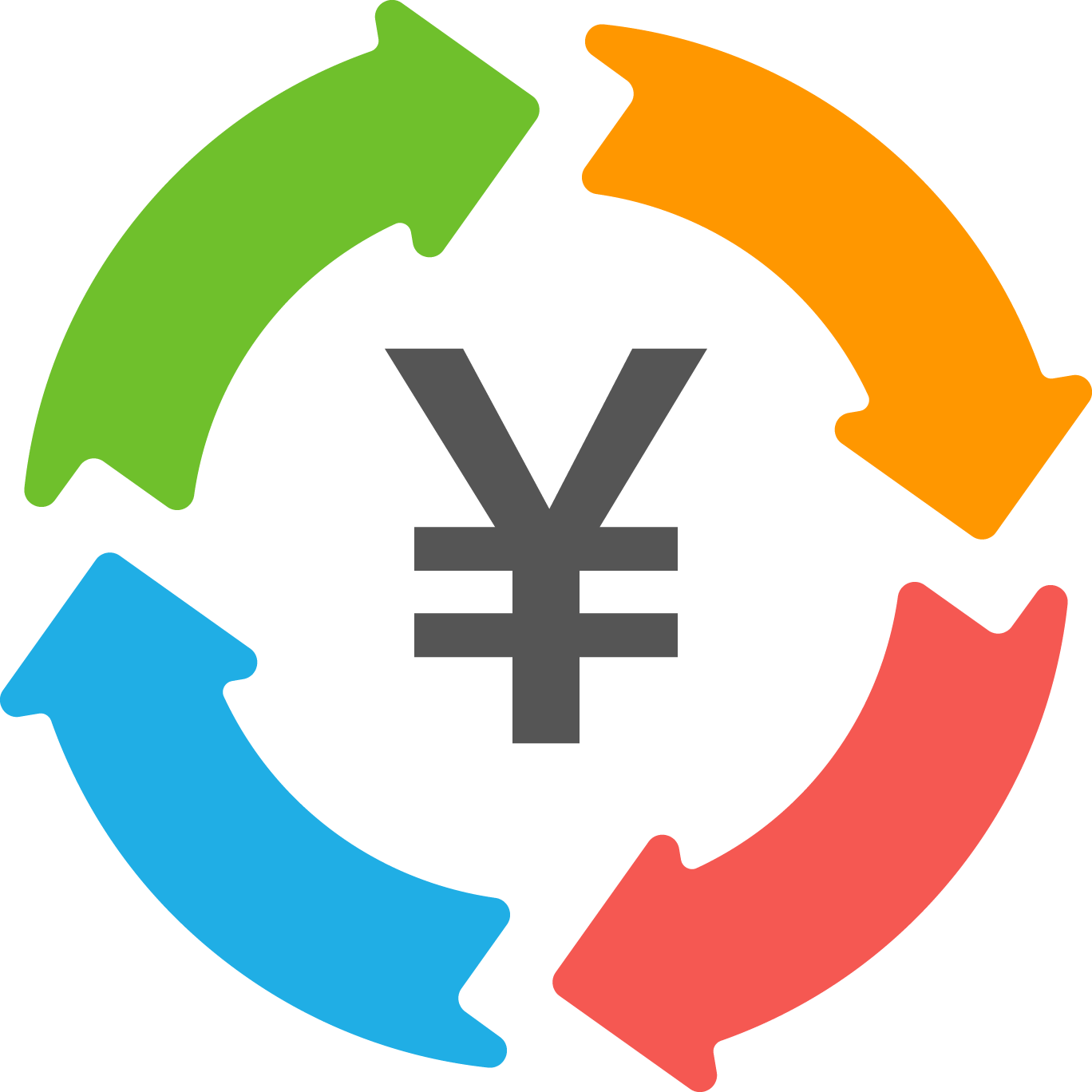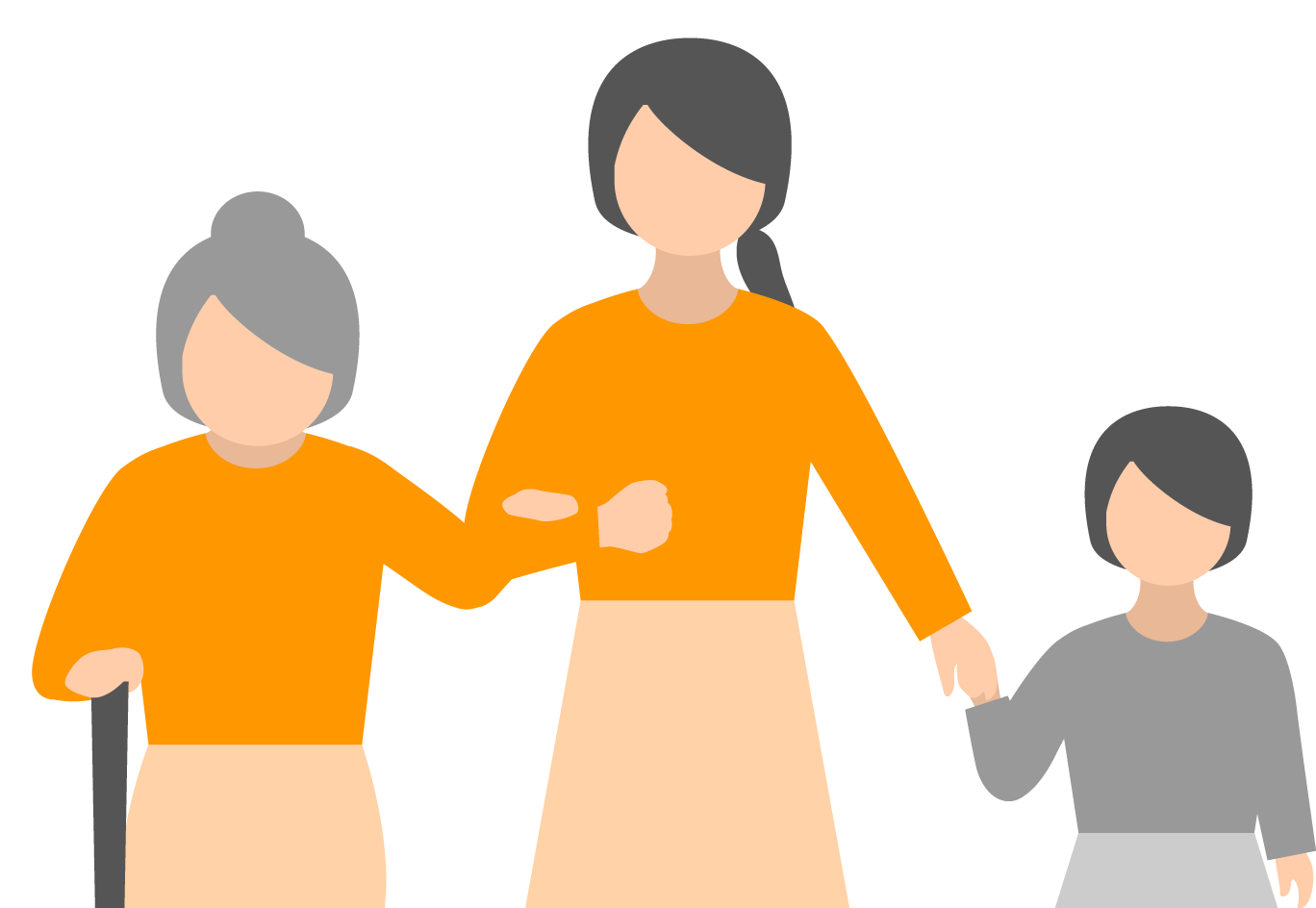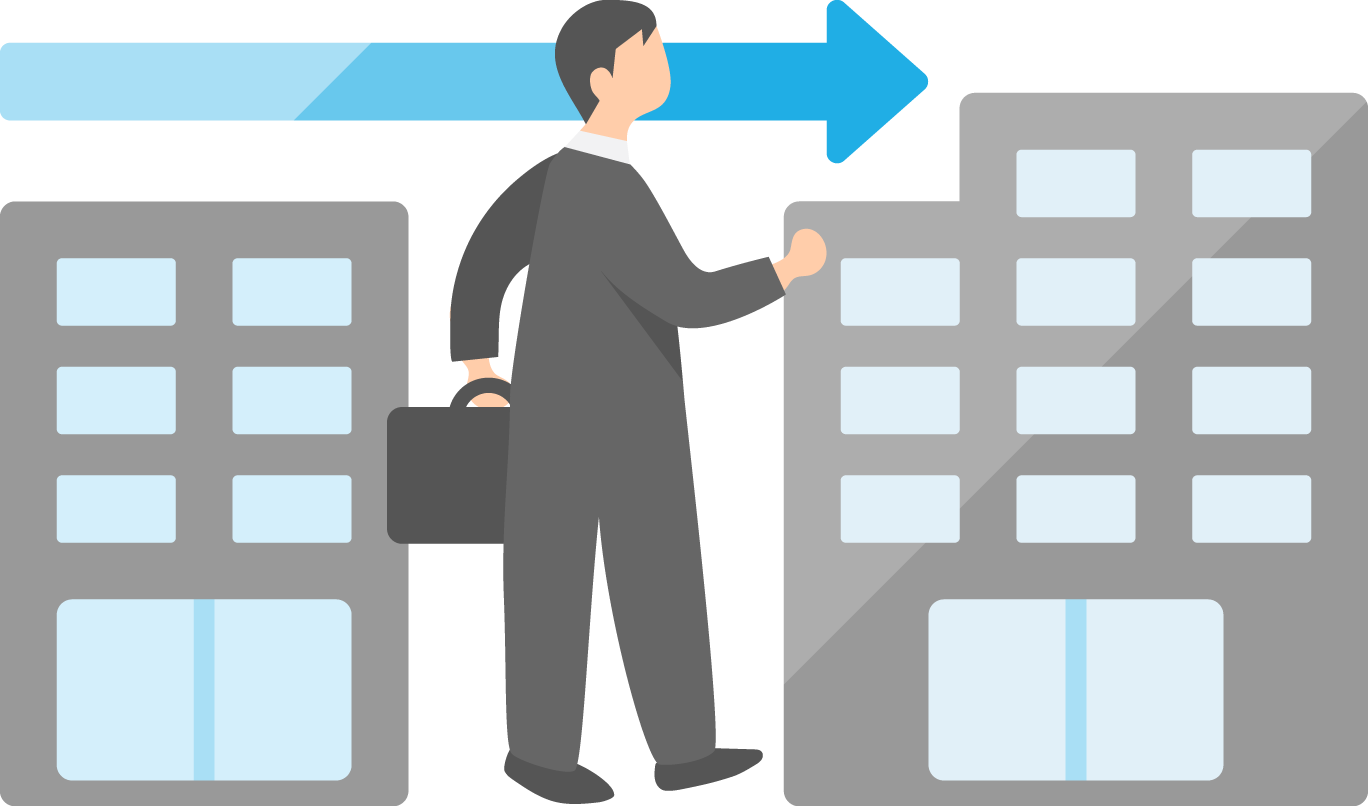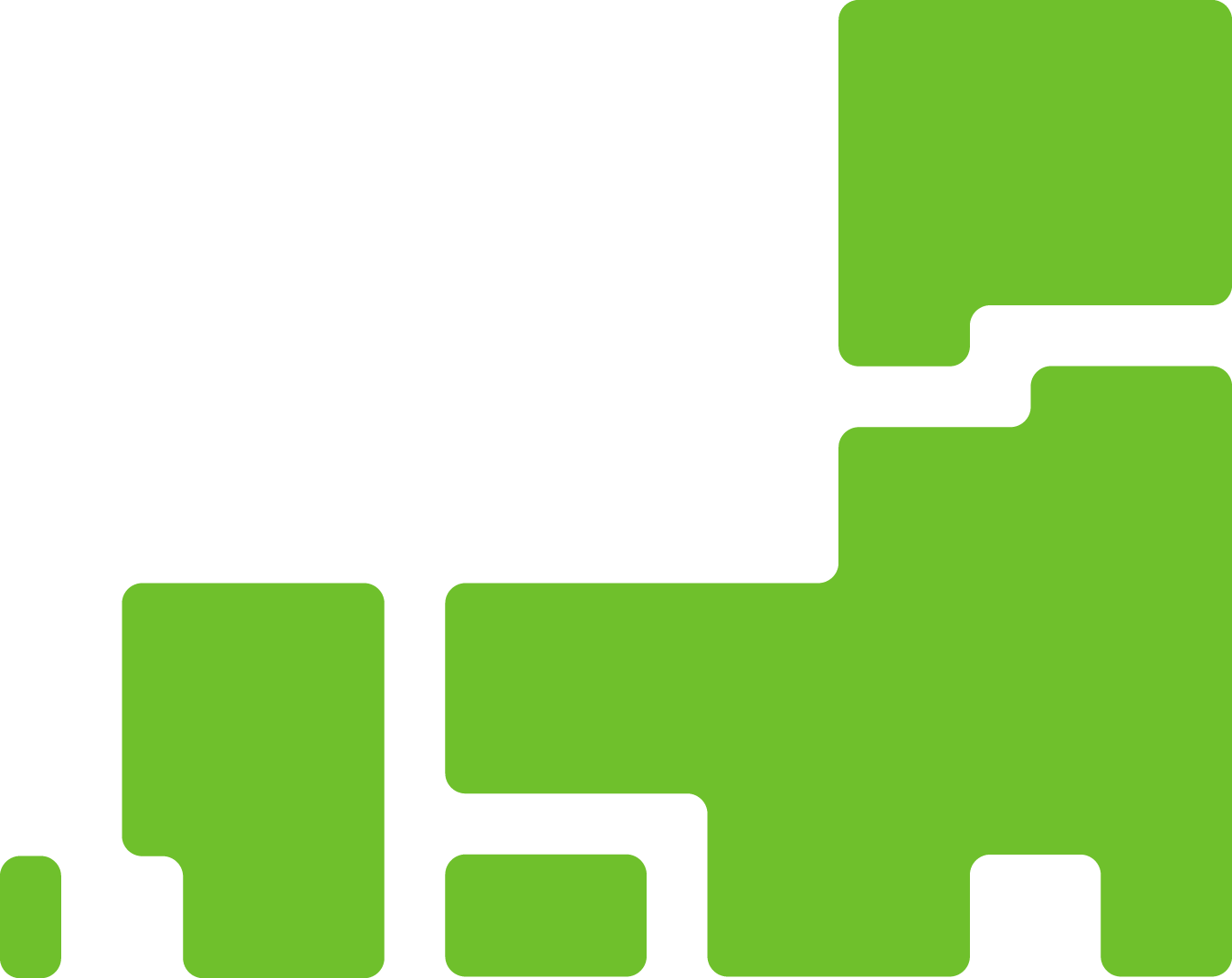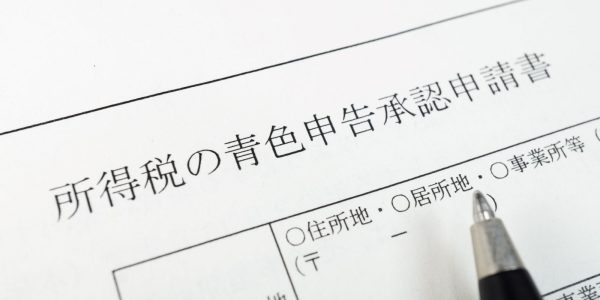個人事業主がもらえる補助金は?助成金・給付金もあわせて解説

事業拡大や資金繰りの手助けになる補助金・助成金・給付金は、個人事業主やフリーランスにとって大きな味方です。今回は、2025年版の各種補助制度を詳しく解説します。また、個人事業主が利用できる減免制度や支援サービスなども紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
個人事業主がもらえる補助金・助成金・給付金とは?
補助金・助成金・給付金とは、いずれも国や地方自治体などから支給される、返済が不要なお金です。
補助金は事業活動支援が目的で、新しい事業の立ち上げや事業拡大などに利用できます。助成金は労働環境整備に関するものが多く、従業員の雇用や人材育成に役立ちます。給付金は生活の安定や特定の目的達成を支援するもので、最近では新型コロナウィルス関連で支給された給付金もありました。
次の章では、代表的な例を確認していきましょう。
| 補助金 | 助成金 | 給付金 | |
|---|---|---|---|
| 目的 |
事業活動の支援
|
雇用安定・労働環境改善
|
生活の安定・特定目的の達成
|
| 管轄 | 経済産業省など | 厚生労働省など | 国や自治体など |
| 審査 | あり(事業計画などの審査) | 原則なし(申請要件を満たすことが必須) | 原則なし(申請要件を満たすことが必須) |
| 金額 |
大きい(数百万〜数千万円以上)
|
小さい(数十万円~)
|
小さい(数万円~)
|
| 給付時期 | 後払い | 後払い | 申請後 |
| 返済 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 注意点 | 上限に達した時点で受付終了 | ||
| 例 | 小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金 | 雇用調整助成金 | 住居確保給付金、特別定額給付金 |
※一般的な制度の特徴をおおまかに比較しています。一部例外がある場合もあります。
※下記に掲載している情報は2025年2月時点のものです。補助制度は予告なく終了したり、補助内容が変更されたりする場合があります。内容の詳細や最新情報は各団体に問い合わせるか、各団体のホームページを確認してください。
個人事業主が利用できる補助金
補助金は、事業者や個人に給付されるお金です。
事業者(法人や個人事業主など)が対象の補助金は、事業者の取り組みをサポートするための資金の一部として給付されるものが多いです。ここでは個人事業主が利用できる補助金のうち代表的な制度を紹介します。
| 名称 | 概要 | 補助金額 |
|---|---|---|
|
|
中小企業等が行うバックオフィス業務の効率化やセキュリティ対策に向けたITの導入等に要する経費の一部を補助 | 最大3,000万円 |
|
|
小規模事業者等が自ら作成した経営計画に基づく販路開拓等の取り組み等に要する経費の一部を補助 | 最大5,000万円 |
|
|
中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等かかる費用の一部を補助 | 最大4,000万円 |
|
|
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等を補助 | 最大2,000万円 |
※掲載している情報は2025年2月時点のものです。補助制度は予告なく終了したり、補助内容が変更されたりする場合があります。内容の詳細や最新情報は各団体に問い合わせるか、各団体のホームページを確認してください。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業等が行うバックオフィス業務の効率化やセキュリティ対策に向けたITツールなどの導入を支援するため、それに要する経費の一部を補助する制度です。補助額や補助率、対象となる経費は、申請する枠や類型によって異なります。
なお、公募は2025年3月31日(月)から受付開始です。
| 目的・支援内容 | 中⼩企業・⼩規模事業者などの労働⽣産性の向上のために、デジタル化やDXに向けたITツールの導⼊を⽀援する |
|---|---|
| おもな申請枠・補助上限・補助率 |
<通常枠>
<インボイス枠(インボイス対応類型)>
<セキュリティ対策推進枠>
※そのほか、複数社連携IT導入枠、インボイス枠(電子取引類型)などあり。 |
出典:中小企業庁「令和6年度補正予算・令和7年度当初予算 サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2025』の概要」を参考に作成
※最新情報及び詳細は、「IT導入補助金2025」でご確認ください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、販路拡大や経営力強化のために行う取り組みに対して、経費の一部を補助する制度です。
通常枠では補助上限額が50万円です。
なお、小規模事業者持続化補助金は2025年も継続される見込みです。
| 目的・支援内容 | 小規模事業者が自社の経営を見直し、販路拡大や経営力強化のために行う取り組みに対して、経費の一部を補助する |
|---|---|
| おもな申請枠・補助上限・補助率 |
<一般型(通常枠)>
※そのほか、一般型(インボイス特例)、創業型、共同・協業型、ビジネスコミュニティ型などあり。 |
出典:中小企業庁「令和6年度補正予算・令和7年度当初予算 持続化補助金の概要」を参考に作成
※最新情報及び詳細は、中小企業庁「中小企業対策関連予算」でご確認ください。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業や小規模事業者などが直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など)に対応するため、新製品・サービスの開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資等にかかる経費の一部を補助する制度です。
「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」の2つが設けられており、製品・サービス高付加価値化枠の補助上限額は従業員の人数によって額が変わり、例えば5人以下であれば最大750万円の補助を受けることが可能です。
| 目的・支援内容 | 中小企業や小規模事業者などが直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など)に対応するため、新製品・サービスの開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資等にかかる経費の一部を補助する |
|---|---|
| おもな申請枠・補助上限・補助率 |
<製品・サービス高付加価値化枠>
<グローバル枠>
※特例措置が適用される場合は、100万円~1,000万円上乗せされる。 |
出典:中小企業庁「令和6年度補正予算・令和7年度当初予算 令和6年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の概要」を参考に作成
※最新情報及び詳細は、「ものづくり補助金総合サイト」でご確認ください。
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金は、中小企業の生産性向上や持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資やM&A・PMIの専門家活用などにかかる経費の一部を補助する制度です。
補助額は申請枠によって異なり、例えば5年以内に親族内継承などを予定している人が対象となる事業継承促進枠の場合は、最大1,000万円の補助を受けることができます。
この補助金は前年まで「事業継承・引継ぎ補助金」という名称でしたが、2025年度から「事業承継・M&A補助金」に名称を変え実施される見込みです。
| 目的・支援内容 | 中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等を支援する |
|---|---|
| おもな申請枠・補助上限・補助率 |
<事業承継促進枠>
※そのほか、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠あり。 |
出典:中小企業庁「令和6年度補正予算・令和7年度当初予算 事業承継・M&A補助金」を参考に作成
※最新情報及び詳細は、「事業承継・M&A補助金」でご確認ください。
個人事業主が利用できる助成金
事業者が利用できる助成金は、おもに人材を雇用した場合に助成されるものが多いです。ここでは、個人事業主が利用できるおもな助成金について解説します。
| 名称 | 概要 | 助成金額 |
|---|---|---|
|
|
職業訓練を実施した際の経費や賃金の一部を助成 | 最大1,000万円 |
|
|
安定的な就職が困難な求職者を一定期間試行雇用した事業者に助成 | 最大5万円を3カ月間支給(一般トライアルコースの場合) |
|
|
生産性向上のための設備投資と、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を助成する制度 | 最大600万円 |
| 雇用機会が不足地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、その地域に居住する求職者を雇い入れた場合に助成 | 最大800万円 | |
| 特定の要件を満たした従業員を新たに雇い入れた事業者に対して助成 | 最大240万円(特定就職困難者コースの場合) | |
| 離職を余儀なくされた労働者の再就職支援や職業訓練の実施、早期の雇い入れ等を行う事業者に対して助成 | 最大100万円 | |
| 新しく中退共制度に加入する事業主や掛金月額が1万8,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対して助成 | 助成の種類によって異なる |
※掲載している情報は2025年2月時点のものです。助成制度は予告なく終了したり、助成内容が変更されたりする場合があります。内容の詳細や最新情報は各団体に問い合わせるか、各団体のホームページを確認してください。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、事業者が雇用する従業員に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練を実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が支給される制度です。
人材開発支援助成金には、6つのコースが設けられており、助成額や受給要件、申請方法などは各コースによって異なります。申請期間はそれぞれ職業訓練終了後2カ月以内です。
なお、障害者職業能力開発コースは、2024年4月に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給業務を行う「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」へ移管されました。
| 目的・支援内容 | 事業者が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練等を計画的に実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
|---|---|
| おもな申請枠・助成金額 |
<人材育成支援コース>
<人への投資促進コース>
※そのほか、教育訓練休暇等付与コース、事業展開等リスキリング支援コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コースあり。 |
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、職業経験の不足などの理由によって安定的な就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介によって一定期間試行雇用した事業者に支給される助成金です。
助成額や受給要件、申請方法などは各コースによって異なります。なお、申請期間はそれぞれトライアル雇用終了後2カ月以内となっています。
| 目的・支援内容 | 安定的な就職が困難な求職者を一定期間試行雇用した事業者に助成 |
|---|---|
| おもな申請枠・助成金額 |
<一般トライアルコース>
※そのほか、障害者トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコースなどあり。 |
出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」を参考に作成
※最新情報及び詳細は、厚生労働省「雇用関係助成金一覧」をご確認ください。
業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた事業者に対して、その設備投資などにかかった費用の一部が支給される助成金の制度です。2024年度の交付申請の受付は2025年1月31日で終了し、2025度の実施については未定となっています。
しかし、令和6年度厚生労働省補正予算案では「施策名:最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金」として297億円が計上されていますので、2025年も業務改善助成金が実施される可能性はあると考えてもよいでしょう。
| 目的・支援内容 | 業務改善目的の設備投資を行った事業者に対して、費用の一部を助成 |
|---|---|
| おもな申請枠・助成金額 |
|
地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金は、人材確保が難しい地域の雇用を促進するための制度です。助成額や受給要件、申請方法などは各コースによって異なります。
| 目的・支援内容 | 人材確保が難しい地域の雇用を促進するため、事業所の設置や雇用を行った事業主に対し助成 |
|---|---|
| おもな申請枠・助成金額 |
<地域雇用開発コース>
※そのほか、沖縄若年者雇用促進コースあり。 |
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、雇用されることが困難と考えられる対象者を雇用した場合に、事業主に一定の条件下で支給される助成金です。
5つのコースが設けられており、助成額や受給要件、申請方法などは各コースによって異なります。
| 目的・支援内容 | 雇用されることが困難と考えられる対象者を雇用した事業主に助成 |
|---|---|
| おもな申請枠・助成金額 |
<特定就職困難者コース>
※そのほか、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コース、成長分野等人材確保・育成コースあり。 |
出典:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」を参考に作成。
※最新情報及び詳細は、厚生労働省「雇用関係助成金一覧」をご確認ください。
早期再就職支援等助成金
早期再就職支援等助成金は、労働者の再就職を企業が支援したり、新しく人材を採用したりする場合に活用できる助成金です。
4つのコースが設けられています。助成額や受給要件、申請方法などは各コースによって異なります。
| 目的・支援内容 | 労働者の再就職支援や新たな人材採用をする事業主に助成 |
|---|---|
| おもな申請枠・助成金額 |
<UIJターンコース>
※そのほか、再就職支援コース、雇入れ支援コース、中途採用拡大コースあり。 |
出典:厚生労働省「早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)」を参考に作成。
※最新情報及び詳細は、厚生労働省「雇用関係助成金一覧」をご確認ください。
中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成
中小企業のための退職金制度である中退共制度に新しく加入する事業主や、掛金月額が1万8,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対して助成されます。
| 目的・支援内容 | 中退共制度に新たに加入する事業主や、既に同制度に加入している事業主が掛金月額を増額する場合に、その掛金の一部を助成 |
|---|---|
| おもな申請枠・助成金額 |
<新規加入助成>
※そのほか、月額変動助成あり。 |
出典:厚生労働省「中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成」を参考に作成
※最新情報及び詳細は、厚生労働省「中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成」をご確認ください。
個人事業主が利用できる給付金・支援金など
次に、個人事業主が利用できる給付金・支援金などについて解説します。
| 名称 | 概要 | 給付金額 |
|---|---|---|
|
|
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内など、一定の要件を満たした場合に家賃額を支給 | 市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3カ月(延長は2回まで最大9カ月間) |
|
|
各都道府県・地域別に実施している支援金 | 地域の各種支援金によって異なる |
※掲載している情報は2025年2月時点のものです。給付制度は予告なく終了したり、給付内容が変更されたりする場合があります。内容の詳細や最新情報は各団体に問い合わせるか、各団体のホームページを確認してください。
住居確保給付金
仕事を辞めたり廃業したりしたことで収入が落ち込み、住まいを失った(または住まいを失うおそれがある)人に対して、原則3カ月間(延長は2回まで最大9カ月間)の家賃額を補助する制度です。
- 世帯の生計をおもに支えている人物が離職・廃業後2年以内である
- 個人の責任や都合ではないのに給与などを得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している
- 休職中の場合は、ハローワーク等に求職の申込をし誠実かつ熱心に求職活動を続けること
といった要件が設定されています。
※最新情報及び詳細は、厚生労働省「住居確保給付金」でご確認ください。
事業促進・継続に関する支援金
各都道府県において地域別に実施している支援金制度です。地域によって支援金の内容は異なりますので、お住まいの地域で対象となる支援金があるのか確認してみましょう。
例えば、下記のような支援制度があります。
- 北海道札幌市:令和6年度観光施設受入環境整備(魅力アップ)補助事業
市内観光施設が行う施設利用単価の増額などに資する受入環境整備に対して、経費の一部を補助する補助事業。 - 宮城県:令和6年度伝統的工芸品産業振興費補助金
伝統的工芸品産業の振興を図るため、伝統的工芸品として国または県の指定を受けた工芸品や、市町村が地場産業として支援している工芸品を製造する者に対して予算の範囲内において経費の一部を支給する補助金制度。 - 石川県金沢市:中心市街地出店促進フォローアップ事業
中心市街地の商店街の活性化を図るための、空き店舗への出店に係る支援と事業継続に向けたフォローアップ。補助対象は小売、一般飲食、生活関連サービス業の中で商店街が希望するもの。
個人事業主が利用できる減免制度や支援サービスなど
ここでは、個人事業主が利用できる減免制度や支援サービスなどについて解説します。
国民健康保険料の減額・減免
国民健康保険料を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者応益割(均等割・平等割)額の2割~7割が減額されます。
また、災害やその他特別の事情により国民健康保険料を納めることが困難な場合は、国民健康保険料の減免や納付猶予を受けられる場合があります。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される保険料は、全額、3/4、半額、1/4の4種類です。
また、20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、承認されると保険料の納付が猶予されます。
開業者向けの支援サービスや制度
近年では、補助金や給付金制度以外にも、個人事業主の開業を支援するさまざまなサービスが登場しています。
サービス内容は提供する企業や各団体によって異なりますが、例えばFPや会計士などの専門家への無料相談会のほか、「開業支援セット」などのように店舗開業に必要な設備や情報をまとめて提供してくれるケースもあります。こういったサービスもうまく活用して、スムーズに開業準備を進めましょう。
補助金・助成金・給付金を利用する際の注意点
補助金・助成金・給付金の制度を利用する際の注意点を解説します。
申請すれば必ず支給されるわけではない
採択件数や予算が設けられている場合は、受給要件を満たしていても支給されないことがあります。また、事業期間が設けられている場合は、事業期間外の支出は経費として認められない(受給の対象外となる)こともありますので、注意が必要です。
手続きに手間がかかる
各制度には公募期間が設けられていることが多く、受給を希望する場合はこの期間内に提出する書類を準備して申請する必要があります。申請書や事業計画書などの提出書類を普段の業務と並行して作成しなければならないため、事前に実施日程などを確認して計画を立てておくとよいでしょう。
申請から支給までに時間がかかる
申請から実際に支給されるまでに時間がかかる場合も多く、受給要件を満たしたあとでなければ支給されないものや、申請から支給されるまで1年以上かかるものもあります。支給されるまで時間がかかることを想定して早めに計画し、利用する必要があります。
まとめ
- 補助金、助成金、給付金は、国や地方自治体などから支給されるお金のことで、原則として返済は不要
- 給付金、補助金、助成金の制度には、さまざまな種類がある
- 給付金、補助金、助成金には、申請から実際に支給されるまでに時間がかかる場合があるなどの注意点もある
個人事業主が申請できる補助金、助成金、給付金、それぞれの違いなどについて解説しました。補助金、助成金、給付金の制度の申請には、煩雑な事務処理が増えるなどのデメリットもありますが、助成金や給付金を活用して生産性向上に向けた設備拡充に踏み出せたり、多様な雇用を行うことで採用活動を安定させたりするなどの効果が期待できるメリットもあります。各制度を利用する場合は、事前に申請から支給までの計画を立てておくことが大切です。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?
- 現金払いだけでいいのか不安…
- カード使える?と聞かれる…
導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。
 ※画像はイメージです
※画像はイメージです
下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。
この記事を書いた人
-160x160.jpg)
中田 真(なかだ まこと)ファイナンシャルプランナー
中田FP事務所 代表/CFP®認定者/終活アドバイザー/NPO法人ら・し・さ 正会員/株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師/元システムエンジニア・プログラマー。給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP®資格を取得。現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。https://nakada-fp.com/