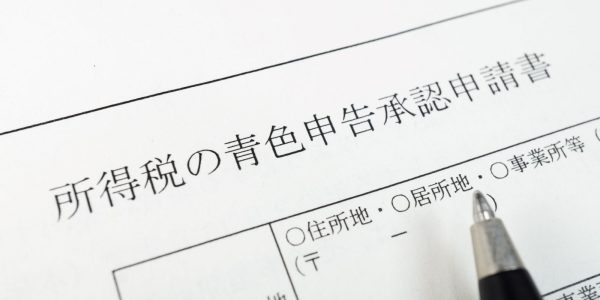会社設立の方法や流れは?必要な手続き・費用・最短で成功させるコツを解説
穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士

「会社をつくるには何をすればいい?期間はどれくらいかかる?」――はじめての会社設立の場合、こうした疑問を抱く人は少なくありません。結論を先に述べると、会社設立は6つのステップで進めることになり、最短2週間程度で設立できるケースもあります。本記事では、会社設立の基本から設立の流れ、設立のメリット・デメリットなどをまとめました。ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
会社設立とは?
会社設立とは、個人とは別に「法人」という新しい人格を生み出し、その名義で契約や資金管理を行えるようにする手続きです。法人になると経営者個人と切り離された「会社の名前」と「会社の財布」ができ、会社の名前で関係機関と取引を行います。
会社設立で社会的信用度や事業展開の選択肢が広がる
詳細なメリットは後述しますが、法人になると信用力が上がることが大きな利点です。例えば、決算書などの情報開示が進むため、金融機関や大手企業は「個人より透明性が高い」と判断しやすくなります。結果として融資・大口契約・人材採用などがスムーズになり、株式発行による大規模な資金調達など個人事業では難しい成長ルートも開けるようになります。
1人でも会社を設立できる?
発起人兼取締役が1人、資本金1円でも株式会社は設立可能です。ただし現実的な運転資金を考慮すると、100万〜500万円程度を準備する企業が多数です。また資本金が多いほど信用は上がるため、将来の融資計画とバランスを取りながら設定しましょう。
会社設立が必要になるおもなケース
では、どのようなときに会社設立を検討すればいいのでしょうか?おもに「税負担」「信用」「資金調達」「許認可」の4つの視点で見ると判断しやすくなります。
法人化で税負担が軽くなる場合
日本の所得税は累進課税制度のため、収入が増えれば増えるほど税率が高くなります。そうなった際、個人にかかる所得税率よりも法人税率のほうが低くなるケースがあります。
例えば、個人事業主の課税所得が900万円を超える頃になると、所得税も多く増える仕組みになっているため、このあたりのラインが一つのボーダーと言えるでしょう。ただしあくまで一般的な目安で個々の状況によっても異なるので、実際にどちらが節税になるのかは、まずは税理士などの専門家に相談してみるのがいいでしょう。
さらなる信用・資金調達を狙う場合
大口の取引や銀行融資では「株式会社○○」の名義が安心材料になります。決算書を提出することで金融機関は財務状況を把握しやすく、融資枠や条件で個人事業より法人のほうが有利になりやすいです。
会社員が独立・起業を検討する場合
会社員をしながら副業で事業を行っているケースもあるでしょう。そしてその副業が本業並みに伸びた段階や、外部投資家を呼び込みたいと考える局面では法人化が不可欠です。とくにIT系スタートアップでは、投資家が株式会社を前提に出資契約を結ぶことが一般的です。
特定の事業を行う上で法人格が必要な場合
行政の許認可が必要な事業や、補助事業などのなかには、法人でなければ認められないものがあります。加えて、特定の入札への参加条件として法人格が求められることもあります。そういった事業を受託したいと考えている場合は、法人化(会社設立)が必須です。
会社形態の種類
日本で設立できる営利目的の会社形態は、現行の会社法で認められている「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。「有限会社」は2006年の会社法改正以降、設立ができなくなっています。
株式会社
最も設立数が多く、社会的な信用度が高い会社形態です。資金を集めるために株式を発行し、会社の所有者は株主となります。株主は、原則として自身が出資した金額までしか責任を負わない「有限責任」であることが特徴です。会社の経営は役員が行い、所有と経営が分離しています。資金調達や事業拡大を目指すスタートアップ、上場やM&Aを視野に入れる企業、また高い社会的信用を重視する事業に最も一般的に選ばれます。ただし、設立にはほかの形態よりやや手間と費用がかかります。
合同会社
合同会社は、2006年に導入された比較的新しい会社形態です。株式会社に比べ設立費用が安く、利益配分を自由に決められる柔軟な組織運営が可能な点が特徴です。また株式会社と同様に出資者全員が「有限責任社員」です。設立コストや手続きを抑えたい中小事業や、利益分配などを柔軟に決めたいメンバー制の事業、個人で事業を始める一人会社など、比較的小規模な事業に適しています。
合資会社
無限責任社員と有限責任社員が混在する仕組みで、かつては家族経営で使われていました。現在は新設例が少なく、地域密着型の小規模事業など、限定的に採用されています。
合名会社
社員全員が無限責任を負うリスクが大きい形態で採用例は少数です。設立手続きは簡単ですが、信頼関係の強い専門家グループなど特殊なケースでのみ選ばれます。
会社の特徴まとめと設立数
会社の特徴や向いている事業、設立数を表でまとめてみました。設立割合は、下記表のとおり株式会社が約7割で、大半をしめていることがわかります。
| 会社種類 | 特徴 | 向いている事業 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 社会的信用が高く、株式で資金調達が可能。決算公告が義務。役員の任期は最長10年。 | 規模拡大を狙うスタートアップ、中小企業全般 |
| 合同会社 | 設立費用が安く、内部自治が柔軟。決算公告不要。 | スモールビジネス、IT・クリエイティブ系の少人数法人 |
| 合資会社 | 無限責任社員と有限責任社員が混在。歴史は長いが設立例は少数。最低出資者数が2人~。 | 家族経営、地域密着型ビジネス |
| 合名会社 | 全社員が無限責任を負う。信用は高いがリスクが大きい。 | ごく限定的(士業の共同事務所など) |
| 会社種類 | 設立数 | 設立割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 100,669件 | 71.17% |
| 合同会社 | 40,751件 | 28.81% |
| 合資会社 | 17件 | 0.01% |
| 合名会社 | 15件 | 0.01% |
会社設立のメリット・デメリット
法人化することで得られるメリットがある一方で、デメリットも存在します。それぞれ解説します。
会社設立のメリット
会社設立のメリットはおもに下記の6点です。
社会的信用度が高まる
法人として事業を行うことで、個人事業主と比較して対外的な信用度が向上します。法人名義での契約は、事業の継続性や安定性を示すと見なされやすく、特にBtoB取引での大きな案件や、新規の取引先開拓において有利に働くことが多くなります。
節税につながる可能性がある
事業の利益が一定額を超えた場合、個人の所得税率よりも法人税率のほうが低くなるケースがあり、節税できる可能性があります。また、役員報酬や退職金を会社の経費として計上できるなど、個人事業主にはないさまざまな節税の選択肢が生まれます。
融資・資金調達がしやすい
決算書を提出することで財務の透明性を示し、借入限度額や金利で個人事業より好条件を引き出しやすくなります。個人事業主では難しかった大型の資金調達も期待できるでしょう。
有限責任になる
前述のとおり、株式会社や合同会社といった会社形態では、出資者(株主や社員)は原則として自身が出資した金額以上の責任を負う必要がありません(有限責任)。これにより、万が一事業が失敗し、会社の負債が出資額を上回った場合でも、個人の全財産を失うといったリスクを限定できます。
決算月の自由設定
会社は事業年度の「決算月」を自由に決めることができます。例えば、事業の繁忙期を避けた時期を決算期に設定することで、棚卸や納税準備を計画的に進めることができます。また、税金が発生する利益の確定時期をコントロールしやすくなり、資金繰りの調整に有利に活用するといった戦略的な対応が可能になります。
社会保険に加入できる
会社を設立すると、経営者自身を含め、原則として厚生年金や健康保険といった社会保険への加入が義務付けられます。これは会社設立によるコスト増の一面でもありますが、経営者にとっては将来受け取る年金額の増加や、傷病手当金・出産育児一時金といった健康保険からの給付が国民健康保険より手厚くなるメリットがあります。
会社設立のデメリット
会社設立のおもなデメリットは下記の3点です。
設立・維持・解散に費用や手間がかかる
会社設立時には、登録免許税や定款認証費用などの法定費用に加え、司法書士や行政書士への報酬といった初期費用がかかります。設立後も、法人住民税や法人税の申告、社会保険の手続き、税務申告書の作成など、個人事業主と比較して複雑で専門的な事務手続きが増加します。また、会社をたたむ場合も一定の費用と手間がかかります。
赤字でも一定の税負担がある
個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税は原則としてかかりません。しかし、法人の場合は、たとえ事業年度の利益が赤字であっても、「法人県民税・市民税の均等割」が課税されます。自治体によって金額は異なりますが、年間数万円程度の負担が必ず発生するため、特に事業開始当初や業績が不安定な時期は資金繰りに注意が必要です。
社会保険の加入義務がある
会社を設立すると、経営者自身を含め、原則として社会保険(厚生年金、健康保険)への加入が義務となります。社会保険料は、会社と従業員(役員含む)で折半して負担しますが、会社負担分が発生するため、個人事業主の頃と比較して社会保険料の負担が増加します。
会社設立の流れ
ここでは、会社形態の中では最も手間がかかる株式会社を例に、設立の流れをご紹介します。冒頭でも紹介したとおり、おおまかに6つのステップで行います。
STEP1.事前準備(事業検討)
まずは事業計画を練り、「何を、誰に、いくらで」提供するのかを書き出します。売上見込みと固定費を洗い出せば、必要資本金や融資額の輪郭が見えてきます。ビジネスモデルが明確なら、定款の作成もスムーズです。
STEP2.会社の骨格、基本事項を決める
会社名・所在地・事業目的・資本金・役員構成など、会社の基本となる情報を確定し、商号の類似チェックも忘れずに行います。会社名は同一住所でなければ重複していても登記できますが、ネット検索で埋もれない独自性を意識しましょう。本店所在地は自宅でも構いませんが、賃貸契約で「法人登記不可」とされていないか必ず確認してください。
STEP3.会社用の印鑑を作成
会社名が決まったら会社のハンコ(実印・銀行印・角印)を用意しましょう。安価なものでも登記できますが、チタンや水牛のような耐久性の高い素材を選ぶと長く使えて安心です。なお、銀行印と実印を同じにすると管理が煩雑になり紛失リスクも高まるので、用途ごとに分けるのが無難です。
STEP4.定款の作成・認証
会社の根本ルールとなる定款を作成します。株式譲渡の制限や公告方法などは、会社設立後に変更する場合、株主総会の決議や登記変更手続きが必要となり、手間とコストがかかる項目もあるため慎重に決めましょう。電子定款は専門ソフトか代行サービスを使えば初心者でも作成できます。なお、電子定款を選ぶと印紙代4万円が不要です。
STEP5.出資金(資本金)の払い込み
定款が認証されたら、次に資本金を発起人の銀行口座に振り込みます。「資本金として用意したお金」ということを明確にする必要があるため、誰が出資金を払込んだか分かる「振込」で入金しましょう。
STEP6.会社設立の登記申請
書類が揃ったら法務局の窓口かオンラインで設立登記申請します。オンライン申請は専用サイト(登記・供託オンライン申請システム)から可能で、自宅から申請できるのはもちろん、窓口より受付時間が長いのが利点です。また電子申請の場合、進捗状況を把握できるのも便利です。受理されれば、数日以内に登記完了通知が届き、晴れて会社が誕生します。
会社設立後に必要な対応
登記後も数カ月は届出が集中します。提出が必要な書類を各窓口に確認の上、スケジュール表を作り、期限を逃さないで手続きするようにしましょう。
税務署・自治体に各種届出を出す
登記が終わったら速やかに各種届出を提出します。例えば税務署には法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、適格請求書発行事業者の登録申請書などを出し、各自治体にも法人設立届出書や定款の写し等を提出します。
特に青色申告は期限を過ぎると適用されず、節税メリットを受けられないので要注意です。また、企業間取引がメインの事業であれば、取引をするためにインボイス制度の登録(適格請求書発行事業者の登録申請)は実質的に必須と言えるでしょう。
社会保険・労働保険の手続き
会社設立後の社会保険・労働保険の手続きは、提出期限が非常に短いため特に注意が必要です。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、会社設立の事実発生から5日以内に年金事務所へ、労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に労働基準監督署やハローワークへ、それぞれ届け出る必要があります。窓口が複数に分かれており、手続きが遅れると罰則や追徴金の対象にもなるため、登記完了後すみやかに準備を進めましょう。
法人口座の開設
法人口座の開設では、銀行は共通して「事業に実体があるか」を厳しく審査します。そのため、定款や事業計画書を準備し、事業内容を明確に説明できるようにしておくことが大切です。
最近では、本店所在地がバーチャルオフィスの場合や、資本金が極端に少ない場合、また定款の事業目的が多すぎる場合などは、事業実体が疑われ、審査に時間がかかったり、開設を断られたりするケースも出ています。会社を設立する段階から、口座開設のことも念頭に置いておくと良いでしょう。
よりスムーズな開設を目指すなら、法人設立の登記前に銀行へ事前相談に行くのも有効な手段です。
従業員を雇う場合の対応
労働条件通知書の交付、36協定の締結、給与計算ソフトの導入など、雇用開始前に整えておくべき実務は多岐にわたります。創業期から労務管理の仕組みを整えておきましょう。また、体制が整ったら採用活動も開始しましょう。
商工会議所への加盟検討
もし、地域密着型の事業であれば、商工会議所への加入を検討してみてもいいでしょう。経営者の集まりなので、その地域での経営に必要な情報も入手しやすい上、取引先が増えたり、提携したりなどのメリットが得られます。また、40歳未満の若手経営者が集まる「青年部」では、同じ事業の悩みや境遇を共有できる仲間を見つけるきっかけになるでしょう。
店舗開業の準備
店舗型ビジネスの場合は、物件契約や内装工事、設備の手配などを行います。特に、店舗で使うレジや在庫管理の仕組みを早期に整えることで、後々スタッフ教育やオペレーションが格段に楽になります。例えば、POSレジアプリの『Airレジ』なら0円で使える上、2店舗目以降も0円と初期投資を抑えて導入できます。また、売上を自動集計し在庫を見える化できるなど、効率的な店舗運営が可能になります。
会社設立にかかる費用
この章では会社設立にかかる費用について、株式会社を例に確認しましょう。
資本金
一昔前は、株式会社なら1,000万円、有限会社でも300万円の資本金が必要でした。今はその規制が撤廃され、法的には1円から設立できます。とはいえ、実際に1円で設立することは少なく、取引先や銀行の印象も考慮すると実際には100万円以上を用意するケースが多数です。一方で資本金を増やしすぎると、設立初年度でも消費税の課税事業者の対象になったり、法人住民税の均等割が高くなったりと、税金の面で不利になるケースもあるため、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
法定費用
法定費用は、会社設立に関する届出を行政に提出するときにかかる費用のことです。おもに「会社の設立登記費用」「定款関連の費用」がかかります。
設立登記時には登録免許税がかかりますが、最低金額は株式会社で15万円、合同会社で6万円と定められています。定款は認証に1万5000円~5万円、印紙代で4万円かかります。ただし、電子化すれば印紙代不要になるため、電子定款で申請する会社も増えています。
印鑑作成費用
実印・銀行印・角印の価格は素材で上下しますが、数千円~数万円かかります。何度も購入するものでもありませんので、チタンや黒水牛など欠けにくい素材、長持ちする素材を選びましょう。紛失防止のために、まとめて収納できるケースも購入しておくと安心です。
専門家への依頼費用
専門家への依頼費用はケースバイケースですが、書類作成から登記申請までワンストップで依頼すると数万~十数万円程度かかります。さまざまな情報を自分で調べる時間を短縮できるため、開業時に事業準備を最優先したい方には有効な選択肢となります。
会社設立を最短日数で行うポイント
会社設立をなるべく早く行いたい場合、「電子化」「不備&差し戻しゼロ」「形態を迷わない」が最短化のポイントです。下記で詳しくみていきましょう。
オンライン登記申請をフル活用
電子定款と電子署名をそろえれば、移動時間や窓口提出の待ち時間を削減できます。また、法務省は完全オンライン申請の場合「24時間以内処理」を行っています。データ送信後に法務局が内容を確認し、不備がなければ受理→登記完了となるため、物理的な書類の移動がない分だけスピードアップが望めます。
差し戻しがないように提出書類を確認
設立を最短で進めるためには「書類の差し戻し」がないように注意しましょう。例えば、申請情報の記載ミス、添付書類の不備、印鑑の不備など、小さなミスで再提出になれば数週間は簡単に延びてしまいます。専門家のチェックやクラウドサービスの定款テンプレートを活用し、初回提出で通過できる精度を目指しましょう。
法人形態の選択
スピードを最優先するなら合同会社、信用力と株式調達を狙うなら株式会社と覚えておくと判断しやすいです。これは、株式会社の設立には定款認証が必要ですが、合同会社は不要なためです。後から合同会社を株式会社へ変更することも可能ですが、改めて登録免許税がかかるため、最初に形態を決めると無駄がありません。
1人で会社を設立する場合の注意点
従業員がいない1人会社の場合、いくつか注意点があります。下記でポイントを確認しましょう。
1人会社と個人事業主との比較
1人株式会社は、役員=出資者=従業員という関係でも法的に成立します。ただし、法人住民税や社会保険料が固定費として発生するため、売上が立たない期間はキャッシュアウトが続きます。損益分岐点を把握したうえで法人化するかを検討しましょう。
役員報酬の決め方
役員報酬は会社の経費になりますが、期首から3カ月以内に決定し、その後は原則として変更できません。報酬を高く設定しすぎると会社が赤字になり、低くしすぎると個人の生活費が不足してしまいます。税理士などと相談して、会社と個人の収入のバランスを見極めることが重要です。
相続・名義変更についての検討
代表取締役が突然退任・死亡した場合に備え、株式の承継方法を事前に決めておくと安心です。遺言により後継者に株式を集中的に渡す、家族信託を活用して議決権を分散させるなど、専門家と相談しながら最適な方法を選びましょう。
会社設立時は専門家相談や開業支援を活用しよう
会社の設立準備時には前述のとおりさまざまな作業を行います。スムーズに進めるためにも、外部のサービスをうまく使いましょう。
専門家に相談
司法書士は商業登記のプロ、行政書士は定款作成や行政への届出のプロ、税理士は税務のプロです。それぞれ必要に応じて相談すると安心です。費用はかかりますが、結果として設立スピードが上がり、ミスが削減できます。
開業に関するさまざまな支援
世の中には会社設立、店舗開業を支援するさまざまなツールやサービスが多数あります。例えば店舗・テナント検索なら「Tempodas」、店舗の開業支援としては「開業支援セット」などがあります。「Air ビジネスツールズ」は会計、決済、売上管理・分析、予約・受付管理など14のサービスのなかから、ご自身の事業に合わせて、必要なサービスをひとつから導入できますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
創業時に利用できる代表的な補助金・助成制度
行政や各種団体では創業時や事業運営に活用できるさまざまな補助金・助成金を用意しています。募集時期と条件を必ず確認し、自分の事業に合致する場合はうまく活用しましょう。
会社設立に関するよくある質問
最後に、会社設立に関してよくある質問を確認していきましょう。
Q.どの会社形態が一番多いの?
A.株式会社が最多です。合同会社は年々増加傾向にあり、スタートアップや少人数経営で採用されるケースが増えています。
Q.定款とは何?
A.定款は会社の“ルールブック”です。会社名、住所、事業内容、取締役の人数、公告方法などを記載し、公証役場で認証を受けることで法律上の効力が生まれます。定款で決めた内容は株主総会の特別決議がなければ変更できないため、設立時に慎重に作り込むことが大切です。
| 項目 | |
|---|---|
| 絶対的記載事項 | 会社名、会社の目的、会社の住所、資本金、発起人の名前、住所、発行可能な株の総数 |
| 相対的記載事項 | 株式譲渡制限に関する規定 |
| 任意的記載事項 | 広告の掲載場所、取締役の数、取締役の任期、会社の事業年度 |
Q.会社設立と個人事業主、どちらが良い?
A.ケースバイケースです。売上が少ないうちは個人事業のほうが手続きも税金も軽いですが、課税所得が900万円を超えたあたりから法人化の節税メリットが出始めます。また、複数人で事業を行う場合や、外部から資金調達する場合は早めの法人化が望ましいでしょう。
Q.開業時に外部サービスを活用するとなぜいいの?
A.経営者が本業以外の雑務で手一杯になると、売上拡大のチャンスを逃しかねません。クラウド会計やPOSレジ、集客支援サービスを導入すれば、財務管理や販売管理、広告宣伝などを効率化でき、開業初期のリスクを下げられます。
まとめ
- 法人設立は基本情報決定から登記まで6ステップ。電子定款やオンライン申請を活用すれば最短約2週間で完了できる
- 法人化で信用力向上、節税、資金調達の拡大、有限責任によるリスク軽減が得られる
- 登記後は2カ月以内に各種届出を済ませ、運営基盤を固める必要がある
- 開業準備の際は専門家への相談や開業支援サービスの活用でスムーズに進む
会社設立は「難しい」「お金がかかる」と敬遠されがちですが、実際には6ステップを順にこなせば、最短2週間程度で完了します。設立後も税務・労務・店舗準備とやることは多いものの、専門家への相談やAir ビジネスツールズといった事業者向けサービスを活用すればスムーズに進むでしょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?
- 現金払いだけでいいのか不安…
- カード使える?と聞かれる…
導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。
 ※画像はイメージです
※画像はイメージです
下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。
この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。
-160x160.jpg)
穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士
税理士法人 エンパワージャパン 代表税理士 1981年生まれ 横浜市在住
中小企業こそ日本を支える礎であるという理念から、持続可能な社会・持続可能な企業を創るための「中小企業のための財務支援プログラム」を実施することで強固な財務力を持つ優良企業に導く、中小企業の財務支援に専門特化した税理士事務所を運営するとともに、児童養護施設の児童から地域を支援する税理士へと導く「大空への翼プロジェクト」を行っている。共著「七人のサムライ」や執筆など多数。