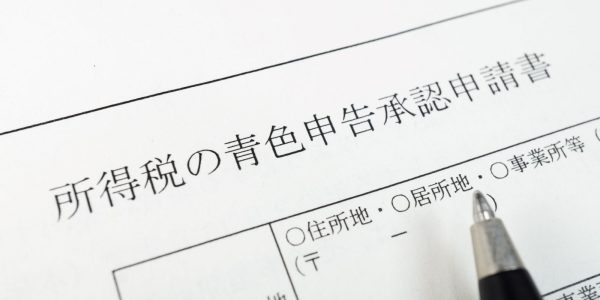飲食店経営で失敗しない!余計なお金を使わずに集客・運営を成功させる秘訣とは?

「飲食店の経営は難しい」とよくいわれます。実際、開業から1年で30%程度が廃業し、3年で50~70%、10年で90%程度が廃業するともいわれます。その原因は「失敗しない開業の方法や運営方法」を知らない経営者が非常に多いからだといえます。
この記事では、これまで飲食店専門のコンサルタントとして多くの店に関わってきた経験から見えてきた、成功した経営者の多くが実践している、余計なお金を使わずに集客・運営を成功させる・失敗しない経営手法を具体的にご紹介します。
この記事の目次
なぜ飲食店経営は難しい? よくある失敗パターン
飲食店の競争は激しく、10年生存率は10%程度といわれています。これほど多くの飲食店が閉店してしまう背景には、いくつかの共通した失敗パターンが存在します。最初に、飲食店の経営に失敗してしまう人にありがちなパターンを確認しましょう。
高すぎる初期投資と回収見通しの甘さ
飲食店が開店してから半年以内に閉店するケースが比較的多い大きな要因は、おもに2つあります。1つは、初期投資(内装工事・厨房設備・居抜き譲渡金など)に多額の資金がかかること。もう1つは、開店してからしばらくは、固定費(家賃・社員人件費・減価償却費など)が先行して出ていくため、軌道に乗る前に開業準備資金を使い切ってしまう回収見通しの甘さです。
飲食業は変動費(食材仕入れ・光熱費・アルバイト人件費など)が高く、利益率も低いため経営の難易度が高い業種です。あまり試算もせずに開業すると、黒字化する前に資金が尽きてしまい、短い期間で閉店するケースが少なくありません。
「おいしければ売れる」は幻想? マーケティング軽視
「飲食店はおいしければ売れる」とだけ考えてマーケティングを軽視している場合、たとえ料理がおいしくても集客に苦戦し、競合に埋もれてしまいます。ターゲット層を明確にし、店のウリを軸に広告やリピート率UPの仕組みを構築する戦略が不可欠です。さらに戦略を計画実行することではじめて、店が認知されていきます。マーケティングを軽視して早期閉店する飲食店も多いのが実情です。
感覚に頼る経営では数字がついてこない
数字をもとに戦略を練る店は、早期に課題を発見し改善できます。逆に、感覚だけに頼る店は、知らないうちに赤字が膨らみ、気づいた時には「時すでに遅し」で撤退を回避できず、閉店するリスクが大きくなります。
特に昨今は、経営状況をデータ化して戦略に活かしていくためのツールも浸透しつつあり、こうした切り替えに乗り遅れた店が閉店していく傾向にあります。
飲食店経営成功の基本の「き」
次に、飲食店経営を成功させるための4つの基本的な考え方について解説します。
明確なコンセプトと立地選び
「ターゲット層(誰に)」「店のウリ(何を)」が曖昧な店では、お客さまのリピート率を上げていくのは難しいかもしれません。また、そのターゲット層が少ない立地では、いくらコンセプトがよくても集客や売上にはつながりにくいでしょう。飲食店を成功させるために、まず、「誰に」「何を」「どこで」提供するのかが重要になります。
魅力的な料理・サービス
飲食店を成功させるためには、魅力的な料理と心地よいサービスの両方が重要です。料理のおいしさはもちろん基本ですが、それに加えて他店にはない食材や話題性のある盛りつけといった「+α」の価値があるといいでしょう。また、心地よい接客サービスは、料理をさらに特別なものにし、お客さまの満足度をアップしてくれます。
効率的なオペレーションと衛生管理
人手不足が続く昨今では、効率的なオペレーションが必須です。例えば、少人数でも営業可能な動線設計や注文と会計を簡略化するタブレットやQRコードの導入などです。また、動線設計をする際には、効率的な衛生管理(トイレの掃除後や会計後などに、手洗いや消毒がすぐできるなど)も考慮すると効果的です。飲食店を成功させるためには、厨房も含めた効率的なオペレーションと衛生管理が必要です。
数字管理とマーケティング
飲食店は日々の数字を見て問題点を発見・改善することが重要です。逆に言えば、数字を見ずに飲食店は経営できません。原価率やFLRコスト率(売上に対する原材料費、人件費、地代・家賃の割合)、利益率などはもちろん、マーケティングの数値化や顧客リピート率など、多岐にわたります。飲食店を成功させるためには、数字管理とマーケティングが重要になります。
飲食店経営に必要な資格や知識
次に飲食店経営に必要な資格や知識について解説します。
必要な資格
飲食店を開業・営業するために、最低限取得・選任しなければならない資格は次の2つです。
食品衛生責任者
食品を取り扱うすべての飲食店に、1店舗ごとに1人の「食品衛生責任者」の設置が法律で義務づけられています。基本的な役割は、食品の取り扱いに関する衛生管理の指導、食中毒予防・衛生チェック、保健所の指導対応などです。
各都道府県の「食品衛生協会」が実施する1日の講習(約6時間)を受講すれば取得可能です。調理師・栄養士・製菓衛生師などの国家資格がある場合は講習を免除される場合もあります。
防火管理者
店舗の収容人数が30人以上の場合、「防火管理者」を選任する必要があります。基本的な役割は、消防計画の作成や点検、避難訓練の実施、店舗内の火災予防管理などです。地域の消防署または講習機関で実施される「甲種・乙種防火管理者講習」を修了する必要があり、所要日数は1〜2日程度です(乙種:1日、甲種:2日が一般的)。
講習修了後に防火管理者として選任できるため、開業準備段階での早めの取得が望ましい資格です。
あると有利な資格や知識
次に、あると有利な資格や知識も紹介します。
調理師免許
調理の国家資格です。飲食店営業には必須ではありませんが、持っていると信頼感と知識の証明になります。調理師免許は、指定の養成学校を卒業するか、または飲食店などで2年以上の実務経験を積んで試験に合格すれば取得できます。
レストランサービス技能士
こちらはレストランでの接客サービスや接客マナー、食品などについて、プロにふさわしい知識を持っていることを証明する国家資格です。料理ではなく「サービス」の専門知識や技術を証明できるため、特に高級店やコース料理を提供するレストランなどでは大きな強みになります。お客さまに質の高いサービスを提供する「おもてなしのプロ」であることが客観的に示せる資格です。
簿記会計の知識
前述のように、数字管理は成功要因のひとつです。数字に強い経営者は圧倒的に有利です。数字に自信がない人は、売上や原価、利益などを可視化できる会計ソフトやPOSレジの分析機能を活用するのも有効です。例えば『Airレジ』や『freee』『マネーフォワード』などは、数字の管理を効率化してくれるツールとして多くの店舗で使われています。
人事、労務管理の知識
労働時間や残業、休憩の法律知識(労働基準法)などの人事、労務管理も飲食店経営には必要です。知識に乏しい場合は、社労士に依頼したり労務管理ツールを活用したりするとよいでしょう。
マーケティング関連の知識
マーケティングは飲食店経営における「第二の厨房」ともいえるほど重要です。ブランディングの基礎やSNS運用(Instagram、LINE公式アカウントなど)の知識はリピート率向上に欠かせません。詳しくない場合は、飲食店経営の専門家に依頼したり、マーケティングツールの活用なども検討しましょう。
集客のコツは有料集客と無料集客をバランスよく
次に、多くの飲食店経営者にとって重要なポイントである「集客のコツ」を解説しましょう。
初期の認知拡大や競合が激しいエリアは有料集客が重要
開業初期や競合が多い都市部・繁華街では「まず知ってもらうこと」が最優先です。
無料の集客方法だけではスピード感に欠け、埋もれてしまうリスクも高いため、短期的に効果が見込める有料の集客方法を活用しましょう。例えば、グルメサイト(ホットペッパーグルメなど)の有料プラン掲載、InstagramやGoogle広告などのWeb広告などが挙げられます。
ただし、店の受け入れ態勢ができていない場合、集客しすぎるとサービスの質が低下し、リピート率低下につながってしまいます。運営状況を踏まえて、どの程度の集客をするかを考えます。また、初動の客足を気にするあまり、さまざまな集客方法に手を出して資金不足が早まった例もあるので注意が必要です。
長期的な資産になる無料で効果的な集客術
有料の集客同様、無料集客の活用も重要です。無料集客は「時間」を使う必要があります。無料でできる代表的な施策としては、SNSの定期発信(Instagram・X・TikTokなど)、Googleビジネスプロフィールの整備と口コミ促進、地域イベントへの参加、店頭でのPOPやチラシ掲示などがあります。
これらは毎日地道にコツコツと続けるのが基本です。すぐに結果が出るわけではありませんが、後々、成果が積み上がっていきます。有料集客+無料集客を戦略的にバランスよく組み合わせるのが、理想的な集客方法といえるでしょう。下記では無料集客の例をいくつか紹介しましょう。
SNSでファンをつくる
InstagramなどSNSへの投稿は、無料で効果的な集客術の1つです。また、ハッシュタグ「#地名グルメ」「#福岡ランチ」などで関連づけたり、口コミに対してコメントを返したり、お客さまの投稿をストーリーズなどでシェアして顧客参加型にしたりすることで、コツコツと認知度上昇やファンの増加につながります。
SEO戦略やGoogleビジネスプロフィールで検索上位に表示
お客さまがネット検索した際に、上位に店舗が表示されれば、自然と人が集まりやすくなります。上位表示のためには、Googleビジネスプロフィールへの登録は不可欠です。店舗の基本情報や魅力的な写真を登録しておくと、エリア名+業態(例:新宿 ワイン)で検索された際に上位に表示されやすくなります。
また、定期的に「投稿」機能で情報を更新するとGoogleからの評価が上がり、より効果的なWeb集客へとつながります。
その他(メディア露出を狙う、店頭アピールなど)
テレビ、雑誌で紹介されたり、ブロガーやインフルエンサーにアップしてもらうことも効果があります。ただし、有料の場合もあるので注意は必要です。また、店頭に目を引く看板やポスターを設置したり、料理の写真を貼るだけでも入店率の向上につながります。LINE公式アカウントによるリピーター客の囲い込みや近隣への定期的なポスティングも長期的な効果が認められます。いくつものお客さまとの接点を増やし、選ばれる理由を増やしていくのがコツです。
経営管理や人材管理のコツは? すべて「見える化」がカギ
次に、経営管理や人材管理のコツを解説しましょう。
原価率は見直してなんぼ。利益を確保する「価格設計」
「忙しいのに利益が出ない」「口コミ評価が高いのに倒産」といった飲食店の多くは、原価率と価格設定の甘さに原因があります。
店舗規模にもよりますが、一般的に飲食店のフード原価率は25~35%が目安とされています。また、「ウリの商品」と「利益率の高い商品」を両立できているかなど、価格設定も「なんとなく」で決めるのではなく、数字にもとづく戦略的な設定が必要です。物価上昇などに柔軟な対応で原価率を見直して、利益を確保する「価格設計」をしましょう。
人手不足でもまわせる「効率的なシフト管理」
昨今、飲食店が直面する最大の課題の1つが、慢性的な人手不足です。しかし、単に高い給料で人を集めるのではなく、限られたスタッフで効率よく店を営業することが重要です。
例えば、曜日・時間帯別の客数データにもとづいて、過不足なく人員配置し、売上に対する人件費率の適正化を図ったり、急な欠勤に対応しやすいシフト共有の仕組みづくりに取り組むなどがポイントです。手書きや表計算ソフトでシフト管理を行うのは限界があるため、シフト管理ツールなどを活用することで大幅な効率化が期待できます。
『Airシフト』は、スタッフとのやり取りやシフト作成を支援するシフト管理サービスです。手間やミスが発生していたアナログなシフト管理を、劇的に効率化できます。また、タイムカード機能やAirの他サービスとの連携により、さらにお店の運営を便利にすることができます。
現場の数字をデータで把握する「スマート経営」
ここまで述べてきたように、感覚や勘に頼る運営では、正確な店の経営状況がわかりません。経営悪化に気づいたときには手遅れ……といったことにならないよう、現場の数字をデータで把握する「スマート経営」に移行することは、飲食店を持続する上で欠かせません。
そこで今の時代にぜひ活用したいのが、レジ業務・売上管理・分析・スタッフ管理などをデジタルで一元化できる管理ツールです。店舗運営の無駄を減らして、数字管理で改善点も見つけられる「スマート経営」を実現できるでしょう。
例えば、『Airレジ』は0円で導入できるPOSレジシステムです。売上やコストが自動集計される『Airメイト』と組み合わせて、売上や原価率などさまざまな情報を「見える化」。あなたのお店の売上向上を強力にサポートします。
【コラム】あのお店で働きたい! を目指そう
飲食店経営において、「お客さまに愛される店づくり」と同じように重要なのが、「スタッフに愛される店づくり」です。人手不足が深刻な昨今、求人にお金をかけてもなかなか人材は集まりません。では、どうすれば「あのお店で働きたい!」と思ってもらえるのでしょうか。
例えば、明るく清潔な職場環境、わかりやすい業務、がんばりを評価する仕組みなどがあれば、スタッフの定着率は格段に上がります。また、店の雰囲気やサービスへの共感が「店に対する愛着」となり、自然とよい接客へとつながっていきます。よい接客を受けたお客さまが「この店で働きたい!」と思い入社した話はよく聞きます。
つまり、「スタッフに愛される店」は「お客さまに愛される店」をつくる基盤でもあります。お客さまにとって居心地がよいだけでなく、スタッフにとっても居心地がよい店を目指すことが、飲食経営には絶対に必要なのです。
【飲食店の規模別】経営で気をつけること
飲食店経営は規模によって強み・弱みが異なります。ここでは、飲食店の規模別の注意点を解説します。
大規模店、多店舗展開
座席数が多く、スタッフも多数在籍する大規模店や、複数の支店を運営する多店舗展開では、誰でも一定の品質の商品やサービスを提供できる仕組みが重要です。店長やエリアマネージャーなどを育て、経営方針の伝達や育成などを任せるマネジメントが求められます。
中規模店
席数が30〜50席前後でスタッフが10人未満、地域密着型の店舗として運営されることが多い飲食店です。競合が多いため埋もれてしまわないように、特にコンセプトの明確化を意識する必要があります。コストを抑えつつ、売上を最大化する戦略が求められるでしょう。
小規模店
席数が10〜20席前後でオーナーが1人または夫婦など少人数で切り盛りする個人飲食店が多いです。小規模店は売上が限られる分、無理な初期投資や人件費をかけないのが鉄則です。「こだわり」やお客さまとの「距離感」などが武器になります。
リピーターが生まれる店と経営失敗する店はここが違う
ここでは、「リピーターが生まれる店」と「経営失敗する店」の違いを解説しましょう。
記憶に残る「お客さま体験」がある
お客さまはすべてリピーターになる見込みがあります。一度来店し、「また来たい!」と思える「お客さま体験」があるかどうかでリピーターになるお客さまと、二度と来店しないお客さまに分かれます。
「お客さま体験」とは、驚きと感動がある魅力的な料理だったり、ホスピタリティあふれる接客であったりと、さまざまな要素から生まれます。お客さまがお店にいらっしゃる間に、料理、接客、しつらえ、価格、空気感など、あらゆる要因を結集した総合力を、お客さまが「居心地よい」「また来たい」と感じて記憶に残るかどうかが分かれ道です。
お客さま体験を構成する要素のバランスが多少悪くとも、総合力として一定の魅力があればリピート率が上がっていき、必然的に人気店になっていくでしょう。
再来店を促す「仕組み」がある
リピート率を上げるには、来店からお帰りになるまでの間に、記憶に残る体験をたくさんしていただく必要があります。さらに再来店のきっかけとなるポイント提供や適切なタイミングでのご案内送付など、再来店を促す「仕組み」が整っています。
DXによる業務効率化で人の力を活かす
再来店を促す仕組みを運営していくためにも、重要なのがDXによる業務効率化です。DXとはITやデジタルツールを活用して業務を効率化し、さらなる価値を生み出していく取り組みです。リピーターが生まれる店は、受発注や売上データの自動集計やシフト作成など、ツールを使って効率化できる部分は効率化し、来店時の心を込めたおもてなしなど、人にしかできない業務に人が集中できる体制を整えています。まずはDXの手はじめに、ITツールの導入からはじめてみましょう。
「ITは苦手」でもはじめられるデジタル活用

「ITは難しそう」と感じている飲食店経営者は多くいますが、最近では、専門知識がなくても使えるツールが増えています。
例えば0円で導入できるPOSレジアプリ『Airレジ』は、iPadまたはiPhoneにアプリを入れるだけで、すぐに使いはじめられます。 操作はタブレット画面をタッチするだけなので、レジ操作がはじめての方や、ITが苦手な方でも安心です。会計はもちろん、売上管理・商品登録・在庫管理まで一元化でき、日々の業務を大幅に効率化できます。さらに、『Airペイ』を使えば、クレジットカードや電子マネー、バーコード決済などにも対応でき、キャッシュレス対応がスムーズに行えます。『Airリザーブ』は、ネット予約の受付や顧客情報の管理ができる予約システムで、電話対応の負担を軽減しながら機会損失を防ぎます。便利に活用して、人手不足を緩和し、各種データを使って正確に経営状況を把握しましょう。
0円で使えるPOSレジアプリ『Airレジ』について詳しく見る
個人店こそITツールで差がつく
大規模店と違い、個人店は人手も時間も限られています。だからこそ、ITツールの活用によって日々の業務の効率化をおすすめします。
例えば『Airメイト』は、レジ・在庫・売上データを連動させて手入力をなくす経営管理サポートシステムです。転記ミス減少や業務効率化につながるのはもちろん、月次レポートで経営課題をわかりやすく見える化してくれるため、スタッフ全員の意識を自然に向上させることもできます。このほか、『Airレジ オーダー』はお客さま自身がテーブルから注文を行ったり、ホールでの注文をキッチンやレジに連携するシステムもあります。人手不足や新人の育成に時間を割けない飲食店の強力な武器になります。こういったツールを使った効率化により、顧客情報や来店履歴データを活用してリピートしてくださったお客さまにより質の高い体験を提供するなどの対応が可能になります。個人店こそITツールで差がつく。ぜひ詳しい説明をご確認ください。
業務の自動化で「人にしかできない仕事」に集中
「人にしかできない仕事」とは、料理をつくる調理やお客さまへのサービングやさまざまな応対などの接客などです。一方で、売上集計、伝票確認、予約確認、シフト調整などはツールに任せられます。
例えば『Airシフト』は、スタッフのシフト希望をスマホで簡単に集めたり、シフト表を自動作成できるクラウド型の勤怠管理ツールです。紙やExcelでの管理と違い、共有ミスや確認の手間を減らせるので、店長やマネージャーの業務負担が大幅に軽減されます。業務の一部を自動化すれば、スタッフはより「お客さまとの関係構築」に集中できます。結果として、「お客さまに愛される店」「スタッフに愛される店」へとつながります。
飲食店経営の成功事例
ここまで飲食店経営のポイントの1つとしてITツール活用やDXをご紹介してきましたが、実際の飲食店ではどのように活用され、成果を上げているのでしょうか。ここでは「Air ビジネスツールズ」を導入した店舗を例に、業務効率化と売上アップを実現した3つの飲食店事例をご紹介します。
CASE01.喫茶店「自家焙煎珈琲みじんこ」
オペレーション改善でサービスの質を高め10%の売上アップ
本格的なコーヒーと「ホットケーキ」が人気の喫茶店「自家焙煎珈琲みじんこ」。SNSでの人気拡大でお客さまが増加した一方、手作業のオペレーションでは待ち時間が長くなるという課題を抱えていました。
「そこで導入をしたのが『Airレジ』と『Airペイ』です。二つのサービスを連携して使ったところ会計と決済がスムーズになり、スタッフ数を増やすことなく、お客さまの待ち時間を短縮させることができました。……業務オペレーションがスムーズになってから、お客さまへのサービスにも集中できています。これまで力を入れたくても、なかなかできなかった商品説明などを丁寧にできるようになり、以前に比べて売上が10%も伸びました」
CASE02.居酒屋「サカバ イッチ」
注文時のオペレーションが『Airレジ オーダー』の活用で驚くほどカンタンに解決
酒粕おでんと串カツが名物の居酒屋「サカバ イッチ」。2階建ての広い店内を少人数で運営するうえで、会計場所の固定化やスタッフの移動負担が課題でした。そこで導入したのがAirの業務改善サービスでした。
「『Airレジ』と『Airペイ』、『Airレジ オーダー』のハンディの連携後、注文から提供、会計までのオペレーションがスムーズになり、売上が1.5倍に伸びました。要因としては、どのテーブルの注文でも自動でキッチンに連携されることで、スタッフのミス防止やお客さまへの提供スピードアップにつながり、時間当たりの客単価が向上したためです。
また、テーブルの注文内容もレジに自動に反映されることで、会計時に新たに打ち込む必要はなく回転数も向上しています。そして、効果は売上だけにとどまらず、人件費の削減にもつながりました。効率的なオペレーションを組めるようになったことで、これまで4人で回していたシフトを3人で回せるようになったのです。人手不足の時代、少ない人員で効果的に営業ができるメリットは大きいです」
CASE03.「肉×日本酒 Fukuyaバル」
近隣の姉妹店をAirで統一し、情報をリアルタイムで共有。お客さまを相互にご案内し、チャンスロス防止で売上が15%アップ
国産黒毛和牛「常陸牛」と厳選日本酒を提供する「肉×日本酒 Fukuyaバル」。浅草で串焼き居酒屋や和菓子店も展開する同社は、多店舗の売上状況をリアルタイムで把握し、スムーズな多店舗展開を目指していました。
「当店では予約台帳アプリ『レストランボード』も活用し、当店と姉妹店の間で送客をしています。これまで姉妹店を紹介しても、その途中で他の店舗に入ってしまったり、電話で店舗に確認しても忙しくて送客できなかったことがありました。現在では、お店に電話をかけなくても、リアルタイムで姉妹店の席の空き状況を確認して『レストランボード』で予約まで取れます。しっかりと席を確保しているので、店までの途中に他店へ行ってしまう心配もありません。チャンスロスがなくなった結果、15%ほど売上を押し上げる効果が出ています。
Air ビジネスツールズを活用しはじめてから、私自身、人と数字を管理する負担が減り、店舗の価値向上につながる商品開発に集中できるようになりました」
まとめ
- 明確なコンセプトと数字管理に基づく経営判断が失敗しない飲食店をつくる
- 人手不足の時代には、デジタルツールの活用で効率的で効果的に
- 「愛される店」への近道は、スタッフが人にしかできない仕事に集中すること
飲食店経営は難易度が高く容易ではありません。しかし、成功者の多くが実践している手法を取り入れて、必要な準備と継続的な成長があれば、「100年続く店づくり」も可能です。
お客さまに愛され、スタッフにも愛される、そんな「100年続く店」づくりを、ITツールなども活用しながら今日から1歩ずつはじめていってください。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
キャッシュレス対応で、お店の売上アップを目指しませんか?
- 現金払いだけでいいのか不安…
- カード使える?と聞かれる…
導入・運用費0円のお店の決済サービス『Airペイ』の資料を無料でダウンロードできます。
 ※画像はイメージです
※画像はイメージです
下記フォームに必要事項をご入力いただき、ダウンロードページへお進みください。※店舗名未定の場合は「未定」とご入力ください。
この記事を書いた人
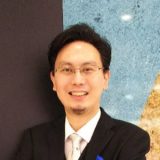
成田 良爾(なりた りょうじ)飲食店専門経営コンサルタント
ヴィガーコーポレーション株式会社代表取締役。厚生労働省公認レストランサービス技能士(国家資格)、文部科学省後援サービス接遇検定準1級、食生活アドバイザー2級など。ミシュランガイド掲載の高級レストランから個人経営の小さな大衆店まで幅広いジャンルの飲食店に携わり、その経験に基づく統計解析および枠にとらわれないアイデアで多くの赤字店を黒字化。「100年続く店づくり」をモットーに、次世代の育成や飲食業の働き方改革などにも力を入れている。食文化普及活動や職業訓練校講師(フードビジネス科)、子育て女性就職支援事業講師なども歴任。メディアへの出演や執筆活動も精力的に行いながら、現在も多くの飲食店経営者のサポートを手がける。オフィスヴィガー http://with-vigor.com/